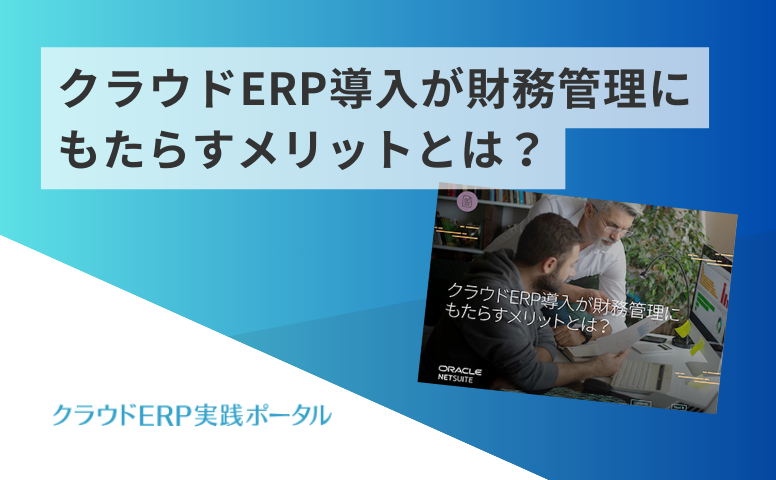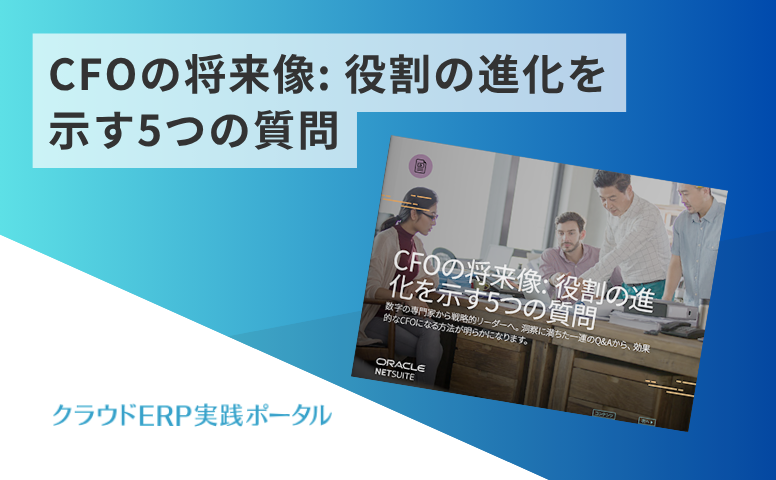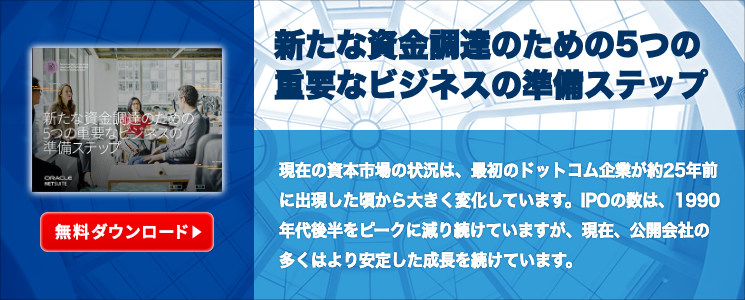非財務情報とは、企業の持続的な成長力を示す上で不可欠な指標です。本記事では、ESG投資の拡大で注目される非財務情報について、基礎知識から有価証券報告書での開示義務化、ISSB基準などの国際動向、企業価値を高める活用法、国内企業の事例まで網羅的に解説します。
非財務情報とは 企業の将来性を示す新たな指標
非財務情報とは、企業の財務諸表には表れない、経営戦略や経営課題、リスク管理、ガバナンス、社会・環境への取り組みなどに関する質的な情報を指します。従来の財務情報が企業の「過去の成績表」であるのに対し、非財務情報は企業の持続的な成長力や将来の価値創造能力を示す「未来の可能性」を測る指標として、その重要性を急速に高めています。
気候変動や人権問題といった社会課題が深刻化し、企業の事業活動に与える影響が無視できなくなる中で、投資家や顧客、従業員といったステークホルダーは、目先の利益だけでなく、企業が長期的に存続し、社会に貢献できる存在であるかを厳しく評価するようになりました。この評価の根拠となるのが、まさに非財務情報なのです。
財務情報との違いをわかりやすく解説
企業の価値を正しく理解するためには、財務情報と非財務情報の両方を理解し、両者の関係性を捉えることが不可欠です。これらは対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。それぞれの特徴と役割の違いを以下の表で整理します。
| 項目 | 財務情報 | 非財務情報 |
| 情報の性質 | 主に過去の実績を示す定量的・金銭的な情報 | 将来の価値創造に関連する定性的・定量的な情報 |
| 時間軸 | 過去・現在(過年度の実績、現在の財政状態) | 未来(将来のリスクと機会、持続的成長の可能性) |
| 主な内容 | 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書など | ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する取り組み、知的財産、人的資本など |
| 具体例 | 売上高、営業利益、純資産、自己資本比率 | CO2排出量、女性管理職比率、従業員エンゲージメント、コンプライアンス体制、顧客満足度 |
| 評価の視点 | 収益性、安全性、効率性 | 持続可能性(サステナビリティ)、ブランド価値、リスク耐性 |
このように、財務情報は企業の経済的な健全性を数字で明確に示しますが、その数字の背景にある企業の強み、抱えるリスク、そして未来に向けた戦略といった「価値創造のストーリー」を読み解くことは困難です。非財務情報は、そのストーリーを具体的に示し、企業の多面的な実態と将来性を明らかにするための重要な鍵となります。
非財務情報が重要視されるようになった背景
近年、なぜこれほどまでに非財務情報が注目されるようになったのでしょうか。その背景には、グローバルな社会経済の変化と、企業を見るステークホルダーの価値観の変容が大きく影響しています。
投資家の視点の変化とESG投資の拡大
非財務情報への関心が高まった最大の要因は、投資家の視点が大きく変化したことです。かつては短期的な利益や株価の上昇を重視する傾向が強かったものの、リーマンショックなどの金融危機や地球規模の環境問題を経て、企業の長期的な成長と持続可能性(サステナビリティ)こそが安定した投資リターンにつながるという考え方が主流になりました。
この潮流を象徴するのが「ESG投資」の急速な拡大です。ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の3つの頭文字を取った言葉で、これらの要素を考慮して投資先を選別する手法を指します。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)をはじめとする世界の主要な機関投資家がESG投資を積極的に推進しており、企業がESG課題にどう取り組んでいるかを示す非財務情報は、今や投資判断に不可欠なものとなっています。投資家は非財務情報を分析することで、財務諸表には現れない潜在的なリスクや、新たな事業機会を捉える企業の能力を評価しているのです。
持続可能な社会の実現に向けた動き SDGsとの関連性
もう一つの重要な背景が、国際社会全体での持続可能性への意識の高まりです。特に、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」は、企業に大きな影響を与えました。SDGsは、貧困や飢餓、気候変動、不平等といった17のグローバルな目標を掲げ、その達成に向けて民間企業が果たす役割に大きな期待を寄せています。
これにより、企業は自社の事業活動がSDGsのどの目標達成に貢献できるのかを明確にし、その取り組みを具体的に開示することが求められるようになりました。SDGsへの貢献は、単なる社会貢献活動(CSR)に留まらず、新たな市場の創出やイノベーション、企業ブランドの向上に直結する経営戦略そのものと認識されています。企業の環境保護活動や人権への配慮、ダイバーシティの推進といった取り組みは、すべて非財務情報として発信され、顧客や取引先、さらには将来の従業員をも惹きつける重要な要素となっているのです。
非財務情報が示す具体的な内容 ESGの3つの側面
非財務情報の中核をなすのが、企業の持続可能性を測る3つの要素、ESGです。ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字を取った言葉です。これら3つの側面から企業の取り組みを評価し、中長期的な企業価値や将来性を判断する材料とします。投資家や顧客、従業員といったステークホルダーは、企業がESGの各課題にどのように向き合い、事業活動に統合しているかを厳しく見ています。ここでは、ESGが具体的にどのような情報を示すのかを詳しく解説します。
E(環境)に関する情報
E(環境)は、企業が事業活動を行う上で、地球環境に与える影響や、環境課題の解決への貢献度を示す情報です。気候変動や生物多様性の損失といった地球規模の課題に対し、企業がどれだけ責任を果たしているかが問われます。単なるコストではなく、新たな事業機会の創出にもつながる重要な要素です。
気候変動への対応 TCFD提言
気候変動への対応は、環境情報の中でも特に重要視されています。その国際的な開示フレームワークとして広く認知されているのが「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」の提言です。TCFDは、企業に対して気候変動がもたらす「リスク」と「機会」を財務情報と結びつけて開示することを推奨しています。
具体的には、以下の4つの項目に沿った情報開示が求められます。
| 開示項目 | 主な内容 |
| ガバナンス | 気候関連のリスクと機会に関する、取締役会の監督体制や経営者の役割。 |
| 戦略 | 気候関連のリスクと機会が、企業の事業、戦略、財務計画に与える実際の影響と潜在的な影響。様々な気候シナリオ(1.5℃シナリオなど)に基づく分析も含まれる。 |
| リスク管理 | 気候関連のリスクを識別、評価、管理するためのプロセス。 |
| 指標と目標 | 気候関連のリスクと機会を評価・管理するために使用する指標と目標。GHG(温室効果ガス)排出量(Scope1, 2, 3)や、再生可能エネルギー利用率などが該当する。 |
生物多様性や資源循環
気候変動と並び、生物多様性の保全や資源循環(サーキュラーエコノミー)への貢献も重要な環境情報です。企業の事業活動は、土地利用、水資源、原材料の調達などを通じて、生態系に直接的・間接的に依存しています。
生物多様性に関する情報としては、以下のようなものが挙げられます。
- 事業拠点周辺の生態系への影響評価
- サプライチェーンにおける森林破壊や海洋汚染のリスク評価と対策
- 自然資本(水、森林、土壌など)の保全・再生への取り組み
近年では、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)のフレームワークも整備され、生物多様性に関する情報開示の重要性がさらに高まっています。
また、資源循環に関しては、従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」型経済から脱却し、製品の長寿命化、リサイクル、再利用を前提としたビジネスモデルへの転換が求められています。開示される具体的な指標には、廃棄物排出量、リサイクル率、水使用量、再生材利用率などがあります。
S(社会)に関する情報
S(社会)は、企業が従業員、顧客、取引先、地域社会といった多様なステークホルダーと良好な関係を築き、社会的責任を果たしているかを示す情報です。企業の評判やブランド価値に直結し、人材獲得や定着にも大きな影響を与えます。
人的資本 ダイバーシティ&インクルージョン
「従業員はコストではなく、価値創造の源泉となる資本である」という考え方が「人的資本」です。従業員の能力や経験を最大限に引き出すことが、企業の持続的な成長に不可欠とされています。2023年3月期決算から、有価証券報告書において人的資本に関する情報開示が義務化され、注目度は一層高まっています。
開示が求められる主な情報には、以下のようなものがあります。
| 項目 | 具体的な指標例 |
| 人材育成 | 研修時間、研修費用、資格取得者数、リスキリングの方針 |
| ダイバーシティ&インクルージョン | 女性管理職比率、男女間の賃金格差、男性の育児休業取得率、障がい者雇用率 |
| 従業員エンゲージメント | エンゲージメントサーベイのスコア、離職率 |
| 労働安全衛生・健康経営 | 労働災害発生率(度数率・強度率)、健康経営に関する認定取得状況 |
多様な背景を持つ人材が、性別や年齢、国籍などに関わらず公正に評価され、活躍できる職場環境を整備しているかが、企業の競争力を示す重要な指標となります。
人権尊重とサプライチェーン管理
企業活動のグローバル化に伴い、自社内だけでなく、製品の原材料調達から製造、販売に至るまでのサプライチェーン全体における人権への配慮が強く求められています。特に、新興国における強制労働や児童労働、低賃金といった問題は、企業のレピュテーションを著しく損なうリスクとなります。
このため、多くの企業が「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「人権デューデリジェンス」と呼ばれる取り組みを進めています。これは、自社の事業活動やサプライチェーンにおいて人権侵害のリスクを特定・評価し、その防止・軽減に努め、実行した取り組みについて情報開示する一連のプロセスです。具体的な開示情報としては、以下のようなものが挙げられます。
- 人権方針の策定と公開
- サプライヤーに対する行動規範の策定や監査の実施状況
- 人権侵害に関する苦情処理メカニズム(ホットラインなど)の設置・運用状況
- 顧客のデータプライバシー保護に関する方針と体制
G(ガバナンス)に関する情報
G(ガバナンス)は、企業統治とも訳され、企業が健全で効率的な経営を行うための仕組みや体制に関する情報です。透明性が高く、公正な意思決定が行われるガバナンス体制は、不正行為や経営判断の誤りを防ぎ、株主をはじめとするステークホルダーの利益を守るための基盤となります。E(環境)やS(社会)への取り組みを実効性のあるものにする上でも、強固なガバナンスが不可欠です。
取締役会の構成と実効性
ガバナンスの中核を担うのが取締役会です。その構成や運営の実効性が、企業価値を大きく左右します。日本の「コーポレートガバナンス・コード」でも、取締役会の役割と責務について詳細な指針が示されています。
開示が求められる主な情報には、以下のようなものがあります。
- 取締役会の規模と、独立した立場から経営を監督する社外取締役の人数・比率
- 各取締役の専門性や経験を一覧化した「スキルマトリックス」
- 取締役会のジェンダーや国籍の多様性
- 取締役会の実効性に関する自己評価の結果と今後の改善策
- CEOの指名や役員報酬の決定プロセスを監督する「指名委員会」「報酬委員会」の設置状況と活動内容
これらの情報を開示することで、企業は経営の透明性をアピールし、意思決定プロセスに対するステークホルダーの信頼を高めることができます。
リスク管理とコンプライアンス体制
企業経営には、事業環境の変化、自然災害、サイバー攻撃、コンプライアンス違反など、様々なリスクが伴います。これらのリスクを網羅的に把握し、事前に備えるための体制を構築しているかどうかが、企業の安定的な成長を支える鍵となります。
リスク管理体制に関する情報としては、全社的なリスク管理委員会(ERM委員会)の設置や、リスクの特定・評価・対応のプロセスなどが開示されます。特に、気候変動や人権、情報セキュリティといった非財務リスクを、経営上の重要リスクとしてどのように管理しているかが注目されます。
また、コンプライアンス(法令遵守)は企業活動の基本です。役員・従業員へのコンプライアンス教育の実施状況や、不正行為を早期に発見・是正するための内部通報制度の運用状況なども、ガバナンスの健全性を示す重要な情報です。役員の報酬が、短期的な業績だけでなく、ESGへの取り組みといった中長期的な企業価値向上に連動した設計になっているかどうかも、投資家が重視するポイントです。
日本における非財務情報の開示義務化の動向
世界的な潮流を受け、日本国内においても非財務情報の開示を制度化する動きが急速に進んでいます。特に、2023年1月31日に公布・施行された金融庁の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正は、上場企業にとって大きな転換点となりました。これにより、これまで任意開示が中心だったサステナビリティ情報の一部が、投資判断の根幹をなす有価証券報告書において義務化され、企業の経営戦略とサステナビリティへの取り組みの連携がより一層強く求められるようになっています。
有価証券報告書での開示義務化とは
今回の改正の核心は、有価証券報告書内に「サステナビリティに関する考え方及び取組」という新たな記載欄が設けられた点です。これにより、企業は自社のサステナビリティ情報を体系的に整理し、投資家をはじめとするステークホルダーに対して明確に説明する責任を負うことになりました。この開示は、単なる情報公開に留まらず、企業の長期的な価値創造能力とリスク管理体制を投資家が評価するための重要な判断材料となります。
サステナビリティに関する考え方及び取組
新設された記載欄では、国際的な開示フレームワークであるTCFD提言などを参考に、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4つの構成要素に沿った情報開示が求められます。これにより、各企業の取り組みを比較検討しやすくなります。
- ガバナンス:サステナビリティ関連のリスクと機会について、取締役会がどのように監督し、経営陣がどのように評価・管理しているかといった体制を開示します。
- 戦略:気候変動をはじめとするサステナビリティ課題が、自社の事業、戦略、財務にどのような影響を与えるかを説明します。特に、気候変動関連のリスクと機会については、TCFD提言が推奨する「シナリオ分析」の結果を踏まえた記載が期待されます。
- リスク管理:サステナビリティ関連のリスクを、全社的なリスク管理プロセスの中でどのように識別、評価、管理しているかを開示します。
- 指標及び目標:サステナビリティ関連のリスクと機会を評価・管理するために用いる指標(例:温室効果ガス(GHG)排出量など)と、その目標を設定・開示します。GHG排出量については、自社での直接排出(Scope1)と間接排出(Scope2)の開示が求められています。
人的資本、多様性に関する記載
サステナビリティ情報の中でも特に重要性が高まっている「人的資本」と「多様性」に関しても、具体的な開示が義務付けられました。これらは、企業の持続的な成長を支える人材戦略の透明性を高め、投資家がその実効性を評価することを目的としています。
具体的には、「従業員の状況」の項目において、人材育成方針や社内環境整備方針、およびそれらに関連する具体的な指標(目標と実績)を記載する必要があります。開示が必須とされた指標には以下のようなものがあります。
- 女性管理職比率
- 男性の育児休業取得率
- 男女間の賃金格差
また、コーポレート・ガバナンスに関する報告書(CGコード)の改訂と連動し、取締役会の多様性(ジェンダー、国際性、職歴など)に関する考え方や、その測定可能な目標と実績も開示の対象となります。これらの情報は、企業が多様な人材を活かし、イノベーションを創出する能力があるかを示す重要なシグナルとなります。
対象となる企業と施行時期
非財務情報の開示義務化は、金融商品取引法上の開示義務を負う全ての有価証券報告書提出企業が対象です。具体的な対象企業と施行時期は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 対象企業 | 有価証券報告書を提出する全ての上場企業など(プライム、スタンダード、グロース市場の上場企業を含む) |
| 対象書類 | 有価証券報告書、事業報告など |
| 施行時期 | 2023年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用 |
| 主な開示項目 |
|
金融庁の動向と今後の見通し
金融庁は、今回の開示義務化を第一歩と位置づけており、今後も国際的な動向を踏まえながら、開示の質と量の両面での向上を促していく方針です。特に、サステナビリティ情報の信頼性を確保するための「第三者保証」のあり方については、重要な検討課題とされています。
また、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が公表したIFRSサステナビリティ開示基準(IFRS S1、S2)との整合性を図るため、日本国内の開示基準を開発するサステナビリティ基準委員会(SSBJ)の活動も活発化しています。将来的には、現在任意とされているScope3(サプライチェーン全体のGHG排出量)の開示や、より詳細な気候変動関連の財務影響の開示が求められる可能性があります。
企業にとっては、これらの動向を単なる規制対応と捉えるのではなく、自社のサステナビリティ経営を深化させ、企業価値向上に繋げるための戦略的な機会として活用していくことが不可欠です。
非財務情報の開示における主要な国際基準とフレームワーク
非財務情報の開示にあたっては、世界中の投資家やステークホルダーが比較・評価できるよう、国際的に認められた基準やフレームワークに準拠することが極めて重要です。現在、複数の基準が存在し、それぞれに目的や対象者が異なります。ここでは、企業が開示を行う上で特に重要となる主要な基準とフレームワークを解説します。自社の事業内容や開示戦略に合わせて、これらを適切に選択・活用することが求められます。
ISSB基準 IFRSサステナビリティ開示基準
ISSB基準は、IFRS財団傘下の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が開発を進める、サステナビリティ開示におけるグローバルなベースライン(共通の土台)となることを目指す基準です。特に投資家の意思決定に有用な情報提供を目的としており、企業の財務諸表とサステナビリティ情報を連結させる点に大きな特徴があります。
ISSB基準は、TCFD提言やSASBスタンダードといった既存の主要なフレームワークを統合する形で開発されており、以下の2つの基準から構成されています。
- IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」:すべてのサステナビリティ関連のリスクと機会について、投資家が企業価値を評価するために必要な情報を開示するための基本原則を定めています。
- IFRS S2号「気候関連開示」:気候関連のリスクと機会に特化した開示基準です。TCFD提言が推奨する4つの柱(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)を基礎としています。
今後、グローバルな資本市場におけるサステナビリティ開示のデファクトスタンダードとなる可能性が非常に高く、日本国内の有価証券報告書における開示義務化においても、このISSB基準が土台となっています。
GRIスタンダード
GRIスタンダードは、オランダに拠点を置く非営利団体グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)が策定した、世界で最も広く利用されているサステナビリティ報告の基準です。ISSB基準が主に投資家を対象とするのに対し、GRIスタンダードは従業員、顧客、地域社会、NGOなど、より広範なステークホルダーを対象としています。
その最大の特徴は「ダブル・マテリアリティ」という考え方です。これは、企業が社会や環境に与える影響(インパクト・マテリアリティ)と、社会や環境の変化が企業に与える財務的影響(財務マテリアリティ)の両側面から重要課題を特定し、報告することを求めるものです。企業活動が外部に与えるインパクトの観点を重視しているため、企業の社会的責任や持続可能な発展への貢献度を評価する上で重要な基準とされています。
SASBスタンダード
SASBスタンダードは、米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)が開発した基準で、現在はISSBを設立したIFRS財団に統合されています。この基準の最も際立った特徴は、77の業種ごとに、企業の財務パフォーマンスに影響を与える可能性が高いサステナビリティ課題を具体的に特定している点です。
例えば、IT業界であれば「データセキュリティ」、食品業界であれば「食の安全と品質管理」といったように、各業界特有のリスクと機会に焦点を当てた開示項目と測定指標が示されています。これにより、投資家は同業他社間の比較を容易に行うことができ、企業のサステナビリティに関する取り組みが、将来の企業価値にどう結びつくのかを具体的に評価しやすくなります。ISSB基準(IFRS S1)においても、業界別の開示項目を検討する際にSASBスタンダードを参照することが推奨されており、その重要性は依然として高いままです。
統合報告フレームワーク
統合報告フレームワークは、国際統合報告評議会(IIRC)によって公表されたもので、現在はIFRS財団に統合されています。このフレームワークは、企業の財務情報と非財務情報を個別に報告するのではなく、両者を統合し、企業がどのようにして短期・中期・長期にわたって価値を創造するのかという「価値創造ストーリー」を包括的に伝えることを目的としています。
中核となるのが「6つの資本」という考え方です。企業は以下の資本をインプットとして事業活動を行い、アウトプットとアウトカム(成果)を生み出すことで、資本を増減させ、価値を創造していくと捉えます。
- 財務資本:資金
- 製造資本:設備、インフラ
- 知的資本:特許、ブランド、組織知
- 人的資本:従業員のスキル、能力、意欲
- 社会・関係資本:顧客、取引先、地域社会との関係性
- 自然資本:水、大気、鉱物などの自然資源
このフレームワークに基づいて作成される「統合報告書」は、企業の全体像と将来の価値創造能力をステークホルダーに分かりやすく示すための強力なコミュニケーションツールとなります。
これらの基準・フレームワークは相互に補完し合う関係にあり、どれか一つだけを選べばよいというものではありません。自社の目的やステークホルダーの要請に応じて、これらを組み合わせて活用していくことが、質の高い情報開示につながります。
| 基準/フレームワーク名 | 策定主体 | 主な対象者 | 目的・焦点 | マテリアリティの考え方 |
| ISSB基準 | IFRS財団 | 投資家、債権者 | 企業価値に影響を与えるサステナビリティ関連のリスクと機会の開示 | 財務マテリアリティ(シングル・マテリアリティ) |
| GRIスタンダード | GRI | 投資家、従業員、顧客、NGOなど広範なステークホルダー | 企業が経済・環境・社会に与えるインパクトの報告 | ダブル・マテリアリティ |
| SASBスタンダード | IFRS財団(旧SASB) | 投資家 | 業種別に財務的影響の大きいサステナビリティ課題の開示 | 財務マテリアリティ(業種別) |
| 統合報告フレームワーク | IFRS財団(旧IIRC) | 主に長期的な視点を持つ投資家 | 財務・非財務情報を統合した価値創造プロセスの説明 | 価値創造プロセスに影響を与える重要事項 |
非財務情報を企業価値向上へつなげる活用法

非財務情報の開示は、単なる義務やコストとして捉えるべきではありません。むしろ、企業の持続的な成長と競争力強化を実現するための強力な「戦略的ツール」です。開示を通じて自社の強みや課題を可視化し、それを経営戦略に組み込むことで、企業価値を飛躍的に向上させることが可能です。ここでは、非財務情報を企業価値向上へつなげるための具体的な4つの活用法を詳しく解説します。
マテリアリティ(重要課題)の特定と戦略立案
企業価値向上の第一歩は、自社にとって本当に重要な非財務課題、すなわち「マテリアリティ」を特定することから始まります。マテリアリティとは、「自社の事業活動が社会・環境に与えるインパクト」と「社会・環境の変化が自社の財務に与えるインパクト」という2つの軸で評価し、優先的に取り組むべき重要課題を指します。
マテリアリティの特定は、一般的に以下のプロセスで行われます。
- 課題の洗い出し:SDGsや各種国際基準、業界動向などを参考に、自社に関連する社会・環境課題を網羅的にリストアップします。
- 優先順位付け:洗い出した課題を「ステークホルダーにとっての重要度」と「自社事業にとっての重要度(リスクと機会)」の2軸で評価し、マテリアリティ・マトリクスなどを用いて優先順位を決定します。
- 妥当性の検証:特定したマテリアリティが適切であるか、経営層や専門家、主要なステークホルダーとの対話を通じて検証し、取締役会で承認を得ます。
重要なのは、特定したマテリアリティを経営戦略や中期経営計画に統合し、具体的な目標(KPI)を設定して進捗を管理することです。例えば、「気候変動への対応」をマテリアリティとして特定した場合、「2030年までにScope1,2のGHG排出量を50%削減する」といったKPIを設定し、その達成に向けた具体的な施策を事業活動に落とし込みます。これにより、非財務情報への取り組みが単なる報告活動に終わらず、事業成長と社会貢献を両立させる原動力となります。
ステークホルダーとの対話(エンゲージメント)を深める
非財務情報は、株主・投資家、従業員、顧客、取引先、地域社会といった多様なステークホルダーとの対話(エンゲージメント)を深めるための共通言語となります。積極的な情報開示と対話は、企業の透明性を高め、ステークホルダーからの信頼を獲得する上で不可欠です。信頼関係は、企業のレピュテーション向上、リスクの早期発見、イノベーションの創出といった無形の資産となり、長期的な企業価値の基盤を築きます。
ステークホルダーごとに、対話の目的や手法は異なります。以下にその一例を示します。
| ステークホルダー | 対話の主な目的 | 具体的な対話手法の例 |
| 株主・投資家 | ESG戦略の理解促進、資本コストの低減 | 決算説明会、ESG説明会、統合報告書、IRミーティング |
| 従業員 | エンゲージメント向上、人材の獲得・定着 | 従業員満足度調査、1on1ミーティング、タウンホールミーティング、社内報 |
| 顧客 | ブランドロイヤルティ向上、製品・サービスの改善 | 顧客アンケート、製品・サービスへのフィードバック収集、SNSでのコミュニケーション |
| 取引先(サプライヤー) | サプライチェーンの強靭化、人権・環境リスクの低減 | サプライヤー向け説明会、CSR調達アンケート、定期的な監査 |
| 地域社会 | 事業活動への理解促進、良好な関係構築 | 工場見学、地域イベントへの参加・協賛、社会貢献活動報告 |
対話を通じて得られた意見や期待を真摯に受け止め、マテリアリティの見直しや経営戦略へのフィードバックを行うサイクルを確立することが、持続的な価値創造につながります。
統合報告書を通じた価値創造ストーリーの発信
統合報告書は、財務情報と非財務情報を単に並べて開示するものではありません。これらを統合し、企業が持つ様々な資本(知的資本、人的資本、自然資本など)を活用して、どのように社会課題を解決し、短・中・長期的に企業価値を創造していくのかという一貫した「価値創造ストーリー」を伝えるための最も重要なコミュニケーションツールです。
優れた統合報告書は、以下の要素を含んでいます。
- 価値創造プロセス:国際統合報告フレームワークが示す「6つの資本(財務、製造、知的、人的、社会・関係、自然)」をインプットとし、独自のビジネスモデルを通じてアウトプット(製品・サービス)を生み出し、社会・環境にポジティブなアウトカム(成果)をもたらすプロセスを明確に図示・説明します。
- マテリアリティと戦略の連動:特定したマテリアリティが、経営戦略や事業活動とどのように結びついているかを具体的に示します。
- 実績と目標:マテリアリティごとに設定したKPIの過去の実績と将来の目標を定量的に開示し、目標達成に向けた進捗状況を報告します。
説得力のある価値創造ストーリーを描くことで、投資家は企業の将来性や持続可能性をより深く理解し、長期的な視点での投資判断を下すことができます。これは、企業のファンを増やし、安定した株主基盤を構築することにも貢献します。
非財務情報を活用した資金調達 サステナビリティ・リンク・ローンなど
非財務情報への優れた取り組みは、企業の資金調達においても有利に働きます。近年、企業のサステナビリティ活動を資金調達の条件に連携させる「サステナブルファイナンス」の市場が急速に拡大しています。
その代表的な手法が「サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)」です。
サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)
SLLは、企業が自ら設定した野心的で具体的なサステナビリティ目標(SPTs: Sustainability Performance Targets)の達成度合いに応じて、金利などの貸付条件が変動する融資制度です。例えば、「GHG排出量削減率」や「女性管理職比率」などをSPTsとして設定し、目標を達成すれば金利が優遇され、未達の場合は金利が引き上げられるといった仕組みです。
SLLの活用には、以下のようなメリットがあります。
- サステナビリティ経営の促進:金利というインセンティブを通じて、全社的にサステナビリティへの取り組みを加速させることができます。
- 企業評価の向上:SLLの契約締結は、企業のサステナビリティへの強いコミットメントを示すことになり、金融機関や投資家からの評価向上につながります。
- ステークホルダーへのアピール:企業の持続可能性への取り組みを対外的に明確に示すことができます。
この他にも、調達資金の使途を環境プロジェクトに限定する「グリーンボンド」や、社会課題解決に貢献する事業に限定する「ソーシャルボンド」など、多様な資金調達手法が存在します。非財務情報への取り組みは、もはやコストではなく、新たな事業機会や有利な資金調達を実現するための重要な経営資源となっているのです。
まとめ
非財務情報は、もはや単なる開示義務ではなく、企業の将来性を示し、企業価値を高めるための不可欠な要素です。ESG投資の拡大を背景に、投資家は環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)への取り組みを重視するようになりました。日本でも有価証券報告書での開示が義務化され、その重要性はますます高まっています。本記事で解説したように、非財務情報を単なる情報開示に留めず、自社の価値創造ストーリーを伝える戦略的ツールとして活用することが、持続的な成長の鍵となるでしょう。
- カテゴリ:
- 経営/業績管理
- キーワード:
- ESG経営