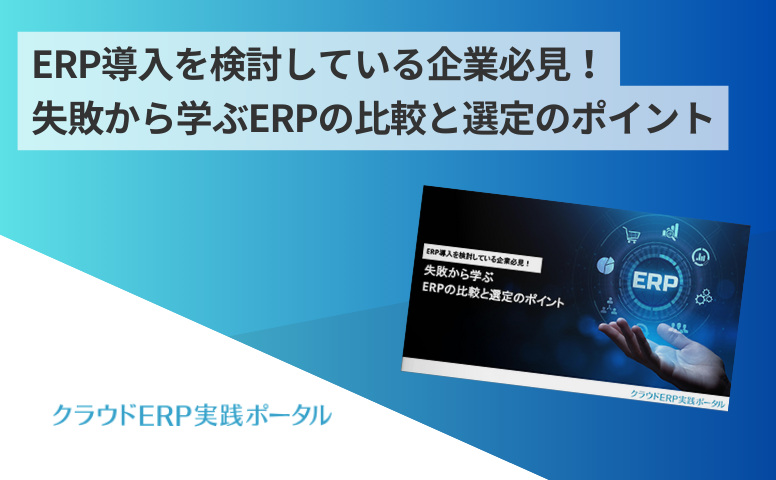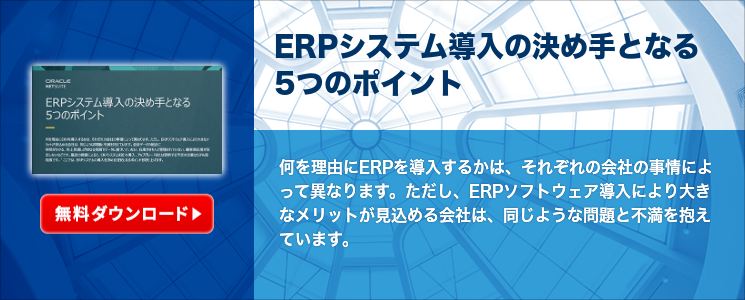ERP導入プロジェクトの成否は、導入前の「目的設定」で決まります。「とりあえず導入する」といった目的の曖昧さが、失敗の最大の原因です。本記事では、経営・業務・ITの視点から企業がERPを導入する目的を網羅的に解説します。さらに、自社の課題を解決し、事業成長を加速させるための具体的な目的設定の進め方から、失敗しないための注意点までを詳しくご紹介します。

ERP導入の目的設定がプロジェクトの成否を分ける理由
ERP(Enterprise Resource Planning)の導入は、単なるシステム刷新に留まらず、企業の経営基盤そのものを変革する一大プロジェクトです。しかし、その影響範囲の広さと投資額の大きさにもかかわらず、残念ながらすべてのプロジェクトが成功に至るわけではありません。その成否を分ける最大の要因、それこそが「導入目的」の明確化に他なりません。
目的が曖昧なままプロジェクトを開始してしまうと、航海図を持たずに大海原へ漕ぎ出すようなものです。ERPは企業のあらゆる課題を自動で解決してくれる「魔法の杖」ではなく、明確な目的地があって初めてその真価を発揮する「羅針盤」なのです。この章では、なぜ目的設定がそれほどまでに重要なのか、具体的な失敗パターンを交えながら解説します。
「導入そのもの」が目的化する失敗パターン
ERP導入プロジェクトは、要件定義から本稼働まで半年から1年以上かかることも珍しくありません。この長期にわたるプロセスの中で、プロジェクトメンバーは日々のタスクに追われ、本来目指していたはずのゴールを見失いがちになります。これが、ERP導入プロジェクトで最も陥りやすい「手段の目的化」という罠です。
「システムを無事に稼働させること」自体が最終目標になってしまうと、次のような問題が発生し、プロジェクトは失敗へと向かってしまいます。
手段の目的化が引き起こす主な問題
| 問題点 | 具体的な内容 |
|---|---|
| コストの増大とスケジュールの遅延 | 本来の目的から外れた機能追加や、現場の個別要求をすべて受け入れた過剰なカスタマイズが発生し、予算と期間が膨れ上がります。 |
| 現場の業務に適合しないシステム | 「とりあえず動くこと」が優先され、実際の業務フローや現場の使い勝手が考慮されず、導入後に「使えない」「かえって非効率になった」という不満が噴出します。 |
| 投資対効果(ROI)の不明瞭化 | 導入によって「何を」「どれだけ」改善したかったのかが曖昧なため、プロジェクト完了後に成果を測定できず、多額の投資が正当化できなくなります。 |
このような事態を避けるためにも、ERP導入はあくまで経営課題を解決するための「手段」であり、決して「目的」ではないという基本原則を、プロジェクト関係者全員が常に意識し続ける必要があります。
経営層と現場の目的意識のズレが引き起こす問題
ERP導入プロジェクトにおけるもう一つの大きな障壁が、経営層と現場担当者の間で生じる「目的意識のズレ」です。それぞれの立場からERPに期待するものが異なるため、このズレを放置したままプロジェクトを進めると、やがて深刻な対立や混乱を引き起こす原因となります。
具体的に、それぞれの視点にはどのような違いがあるのでしょうか。
経営層と現場における目的意識の違い
| 経営層の主な目的 | 現場担当者の主な目的 | |
|---|---|---|
| 視点 | 全社最適・未来志向 | 個別最適・現状改善 |
| 期待する効果 |
|
|
経営層が「全社的なデータ統合による経営の高度化」を求める一方で、現場は「日々の業務が楽になること」を最優先に考えます。この認識の溝が埋まらないままでは、経営層がトップダウンで導入したシステムが現場で全く使われなかったり、逆に現場の要求を鵜呑みにした結果、部分最適の塊のようなシステムが出来上がり、経営判断に資するデータが全く得られないといった事態に陥りかねません。
プロジェクトを成功に導くためには、経営層の描く「全体最適」と現場が求める「個別最適」のバランスを取り、双方が納得できる共通のゴールを設定することが不可欠です。そのためには、プロジェクトの初期段階から各部門の代表者を巻き込み、徹底的に議論を尽くすプロセスが極めて重要となります。
【課題別】企業がERPを導入する主な目的
ERP(Enterprise Resource Planning)を導入する目的は、企業が抱える経営課題によって多岐にわたります。単なるシステム刷新に留まらず、その導入は経営の根幹を改革するポテンシャルを秘めています。本章では、企業がERPを導入する主な目的を「経営視点」「業務視点」「IT視点」の3つの側面から、それぞれの課題解決に焦点を当てて詳しく解説します。
| 視点 | 主な目的 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 経営視点 | 迅速な意思決定と経営の可視化 | データドリブン経営の実現、ガバナンス強化、市場変動への即応力向上 |
| 業務視点 | 全社的な業務効率化と生産性向上 | 部門間連携の円滑化、業務プロセスの標準化、コスト削減 |
| IT視点 | システムの運用保守とDX推進 | 運用保守コストの削減、レガシーシステムからの脱却、変化に強いシステム基盤の構築 |
経営視点の目的:迅速な意思決定と経営の可視化
経営層にとってERP導入の最大の目的は、企業全体の経営状況を正確かつリアルタイムに把握し、迅速で的確な意思決定を下すための経営基盤を構築することです。変化の激しい現代のビジネス環境において、勘や経験だけに頼る経営には限界があります。
リアルタイムなデータに基づいたデータドリブン経営の実現
ERPは、販売、購買、在庫、生産、会計、人事といった企業の基幹業務データを一つのデータベースに統合します。これにより、従来は各部門が個別に管理し、収集・集計に多大な時間を要していた経営情報が、リアルタイムで可視化されます。例えば、最新の売上状況や利益率、キャッシュフローといった重要な経営指標をダッシュボードでいつでも確認できるようになり、客観的なデータに基づいた科学的な経営判断、すなわち「データドリブン経営」が実現します。
グループ全体の経営状況の一元管理とガバナンス強化
複数の子会社や海外拠点を持つ企業グループにとって、各拠点の情報を正確に集約し、グループ全体の経営状況を把握することは極めて重要です。ERPを導入することで、国内外の拠点で異なる会計基準や業務プロセスを標準化し、グループ全体のデータを一元管理できます。これにより、連結決算の早期化はもちろんのこと、全社的な内部統制(ガバナンス)を強化し、不正の防止やコンプライアンス遵守にも繋がります。
市場変動に即応するための経営基盤の確立
現代は、市場や顧客ニーズ、さらには社会情勢が目まぐるしく変化する「VUCAの時代」と言われています。このような環境下で企業が持続的に成長するためには、変化の兆候をいち早く捉え、迅速に対応することが不可欠です。ERPによって経営の可視性が高まることで、変化に強い俊敏な経営基盤を確立し、新たなビジネスチャンスの創出やリスクの早期回避に繋げることができます。
業務視点の目的:全社的な業務効率化と生産性向上
現場の業務担当者にとって、ERP導入は日々の業務プロセスを抜本的に見直し、非効率な作業をなくして生産性を向上させる大きな機会となります。部門最適の考え方から脱却し、全社最適の視点で業務を再構築することが重要です。
部門間の情報連携の円滑化と二重入力の撤廃
多くの企業では、部門ごとに異なるシステムを利用しているため、データが分断される「サイロ化」に陥りがちです。例えば、営業部門が受注した情報を生産部門や経理部門が再度手入力するといった非効率が発生し、入力ミスやデータの不整合の原因にもなります。ERPは、一度入力された情報を全部門でリアルタイムに共有できるため、部門間のスムーズな情報連携を実現し、無駄な二重入力を撤廃します。
業務プロセスの標準化による属人化の解消
「特定の担当者しかできない・わからない」といった業務の属人化は、その担当者の不在時に業務が停滞するリスクや、品質のばらつきを生む原因となります。ERP導入を機に、全社で業務プロセスを見直し、標準化することで、誰が担当しても一定の品質で業務を遂行できる体制を構築できます。これにより、業務の引き継ぎがスムーズになり、組織全体の業務品質と安定性が向上します。
在庫管理・生産管理の最適化によるコスト削減
製造業や小売業、卸売業など在庫を扱う業種において、在庫の最適化は経営の重要課題です。ERPを導入することで、販売実績や需要予測に基づいた適切な在庫レベルの維持が可能となり、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化や、欠品による販売機会の損失を防ぎます。また、生産計画と実績を正確に管理することで、生産リードタイムの短縮や生産コストの削減にも繋がります。
IT視点の目的:システムの運用保守とDX推進
情報システム部門にとって、ERP導入は複雑化した既存システム環境を刷新し、将来のビジネス変化に対応できる強固なIT基盤を構築するという重要な目的があります。
乱立したシステムの統合と運用保守コストの削減
部門ごとに導入された多数のシステムは、それぞれにライセンス費用やサーバー費用、保守・運用を行うための人件費がかかり、ITコストの増大を招きます。これらの乱立したシステムをERPに統合することで、ITインフラをシンプルにし、運用保守にかかるトータルコストを大幅に削減することが可能です。
老朽化したオンプレミス環境からの脱却(レガシーシステム刷新)
長年にわたり改修を繰り返してきた古い基幹システム(レガシーシステム)は、ブラックボックス化し、保守できる技術者の不足やセキュリティリスクの増大といった深刻な問題を抱えています。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」問題にもあるように、レガシーシステムのままではDX(デジタルトランスフォーメーション)の足かせとなり、企業の競争力を著しく低下させかねません。ERPへの刷新は、これらの課題を根本的に解決し、事業継続性を確保するための不可欠な一手となります。
変化に強い柔軟・拡張性の高いシステム基盤の構築
企業の成長戦略(新規事業の開始、M&A、海外展開など)を実現するためには、ビジネスの変化に迅速かつ柔軟に対応できるシステム基盤が不可欠です。近年主流となっているクラウドERPは、機能の追加や外部サービスとの連携が容易であり、事業の成長に合わせてシステムを柔軟に拡張できます。このような変化に強いIT基盤を構築することが、企業のDXを加速させ、持続的な成長を支えることに繋がります。
なぜ個別最適システムでは不十分なのか?ERPがもたらす真の価値
多くの企業では、会計、販売、在庫管理といった部門ごとに最適化されたシステムを導入・運用しています。これらは「個別最適」と呼ばれ、各部門の業務効率を高める上で一定の役割を果たしてきました。しかし、企業が持続的に成長していくためには、個別最適のシステムだけでは不十分であり、むしろ経営の足かせとなるケースが少なくありません。ここでは、個別最適システムの限界と、ERP(統合基幹業務システム)がもたらす「全体最適」の真の価値について解説します。
単体システム(在庫管理など)の限界とデータのサイロ化
個別最適を追求した結果、多くの企業が直面するのが「データのサイロ化」という深刻な問題です。サイロ化とは、各部門のシステムが独立してデータを保持し、組織全体で情報が分断されてしまう状態を指します。この状態は、企業経営において様々な弊害を引き起こします。
例えば、営業部門が販売管理システムに受注情報を入力しても、その情報は自動的に経理部門の会計システムや、工場や倉庫の在庫管理システムには連携されません。その結果、以下のような問題が発生します。
| 問題点 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 二重・三重のデータ入力 | 各部門の担当者が同じような情報をそれぞれのシステムに手入力する必要があり、膨大な手間と時間がかかります。さらに、入力ミスによるデータの不整合が発生するリスクも高まります。 |
| リアルタイム性の欠如 | 部門間のデータ連携が手作業(Excelへの転記など)に頼らざるを得ず、情報の伝達にタイムラグが生じます。これにより、経営層は常に古い情報に基づいて判断を下すことになり、意思決定のスピードが著しく低下します。 |
| 経営状況の不透明化 | 全社的なデータを統合・分析することが困難なため、正確な経営状況を把握できません。在庫の過不足や部門間の業績の偏りといった問題の発見が遅れ、経営判断の質が低下する原因となります。 |
| システム運用・保守の複雑化 | 部門ごとに異なるベンダーのシステムが乱立し、それぞれの保守・運用コストが増大します。また、システム間の連携が複雑になることで、一部の改修が他に影響を及ぼすなど、ITガバナンスの維持も困難になります。 |
このように、個別最適化されたシステム環境は、一見すると各部門の効率を上げているように見えても、企業全体としては非効率な状態を生み出してしまうのです。
ERPによる「全体最適」がもたらす相乗効果
個別最適システムの限界を克服し、企業全体の生産性を最大化するアプローチが「全体最適」です。そして、この全体最適を実現するための強力なIT基盤がERPに他なりません。
ERPは、企業の基幹となる業務(会計、人事、生産、販売、在庫など)の情報を一つのデータベースで統合管理します。これにより、データのサイロ化は解消され、以下のような大きな相乗効果が生まれます。
- 経営の可視化と意思決定の迅速化
全社のデータがリアルタイムでERPに集約されるため、経営層はいつでも正確な経営状況をダッシュボードなどで把握できます。これにより、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた迅速かつ的確な意思決定、すなわち「データドリブン経営」が実現します。 - 全社的な業務効率化と生産性向上
ある部門で入力されたデータは、関連する全部門のシステムに自動で反映されます。例えば、営業担当者が受注情報を入力すれば、そのデータが即座に在庫管理システムに連携され在庫が引き当てられ、同時に会計システムで売掛金が計上されるといった具合です。これにより、二重入力の手間が完全に撤廃され、部門間の連携がスムーズになり、企業全体の生産性が飛躍的に向上します。 - ガバナンス強化と内部統制の実現
業務プロセスが標準化され、システム上にすべてのデータと操作ログが記録されるため、企業の透明性が高まります。承認フローの電子化やアクセス権限の適切な設定により、不正を防止し、健全な内部統制を構築することが可能になります。 - 顧客満足度の向上
正確な在庫情報や生産計画がリアルタイムに把握できるため、顧客からの納期問い合わせに対して迅速かつ正確に回答できます。また、販売履歴や顧客情報を一元管理することで、よりパーソナライズされたサービス提供も可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。
個別最適システムが「点の改善」であるのに対し、ERPは部門の壁を越えて業務プロセスを連携させ、「線」や「面」で企業のパフォーマンスを最大化します。これこそが、ERPがもたらす真の価値であり、多くの企業が導入を目指す理由なのです。
失敗しないERP導入の目的設定|具体的な進め方とポイント
ERP導入プロジェクトの成否は、いかに具体的で、全社的な共通認識を持った目的を設定できるかにかかっていると言っても過言ではありません。目的が曖昧なままでは、必要な機能の要件が定まらず、導入プロジェクトが迷走する原因となります。「導入すること」自体がゴールになってしまい、本来解決すべきであった経営課題が放置されるといった事態を避けるためにも、体系立てられたアプローチで目的を設定していくことが極めて重要です。
ここでは、ERP導入の目的を明確化し、プロジェクトを成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。
ステップ1:現状の経営・業務課題の洗い出し
目的設定の第一歩は、自社が抱える現状の課題(As-Is)を徹底的に洗い出すことです。経営層が感じているマクロな視点での課題と、現場の従業員が日々の業務で感じているミクロな視点での課題、その両方を網羅的に収集することが成功の鍵となります。トップダウンの視点だけでは現場の実態と乖離が生まれますし、ボトムアップの意見だけでは全社的な経営戦略との整合性が取れなくなる可能性があるからです。
課題の洗い出しは、以下のような多角的なアプローチで行うことが効果的です。
- 経営層へのヒアリング:中期経営計画や事業戦略との整合性を確認し、経営視点での課題(例:迅速な経営判断の阻害要因、グループ全体のガバナンス強化など)を明確にします。
- 各部門の責任者・担当者へのヒアリング:部門ごとの具体的な業務プロセスにおける問題点や、部門間の連携における非効率(例:データの二重入力、情報の分断による手作業の発生など)をヒアリングします。
- アンケート調査:より広範な従業員から意見を収集し、潜在的な課題や不満を可視化します。
- 業務フローの可視化:既存の業務プロセスを図に起こすことで、ボトルネックとなっている箇所や非効率な作業を客観的に特定します。
洗い出した課題は、以下の表のようにカテゴリ分けして整理することで、全体像を把握しやすくなります。
| カテゴリ | 課題の具体例 | 関連部署 |
|---|---|---|
| 経営 | 月次決算の確定に時間がかかり、経営判断が遅れる | 経営企画、経理 |
| 経営 | 各拠点の業績データがリアルタイムに把握できない | 経営企画、営業 |
| 業務 | 営業部門と製造部門で在庫情報の連携が取れておらず、販売機会の損失や過剰在庫が発生している | 営業、製造、在庫管理 |
| 業務 | 申請・承認業務が紙ベースで非効率、テレワークの阻害要因となっている | 全部署 |
| IT | 部門ごとに導入されたシステムが乱立し、運用・保守コストが増大している | 情報システム |
| IT | 老朽化した基幹システム(レガシーシステム)のブラックボックス化が進み、事業変化に対応できない | 情報システム |
ステップ2:あるべき姿(To-Be)の定義と目的の具体化
現状の課題(As-Is)を明確にしたら、次にERP導入によって実現したい「あるべき姿(To-Be)」を定義します。これは、ステップ1で洗い出した課題が解決された理想の状態を具体的に描くプロセスです。「業務を効率化したい」といった漠然としたものではなく、「誰が」「何を」「どのように」改善するのかを解像度高く言語化することが重要です。
例えば、「月次決算の確定に時間がかかる」という課題に対しては、「リアルタイムでのデータ連携により、月次決算を5営業日早期化する」といった具体的な目標を設定します。このように、現状(As-Is)とあるべき姿(To-Be)を対比させることで、ERP導入で達成すべき目的がよりシャープになります。
| 現状の課題(As-Is) | あるべき姿(To-Be) | ERP導入によって目指す姿 |
|---|---|---|
| 営業が見積作成時に正確な在庫数を把握できず、納期回答に時間がかかる | 営業担当者がいつでもリアルタイムに全社の在庫状況を把握でき、顧客に即座に納期回答ができる状態 | 販売・在庫情報の一元管理によるリードタイム短縮と顧客満足度向上 |
| 紙の請求書発行・郵送作業に毎月多大な工数がかかっている | 請求書発行から送付までをシステム上で完結させ、手作業をゼロにする状態 | 請求業務の自動化による生産性向上とコスト削減 |
| Excelでのデータ集計・加工に時間がかかり、経営会議に必要なレポート作成が間に合わない | 必要な経営データをいつでもダッシュボードで可視化でき、迅速な意思決定ができる状態 | データドリブン経営の実現による経営スピードの向上 |
ステップ3:目的の優先順位付けとKPIの設定
洗い出した「あるべき姿」は多岐にわたることが多いため、すべての目的を一度に達成しようとすると、プロジェクトが複雑化し、失敗のリスクが高まります。そこで、定義した目的に対して「経営インパクトの大きさ」「実現の緊急性」「投資対効果」などの観点から優先順位を付け、段階的に実現を目指す計画を立てることが賢明です。
さらに、目的の達成度を客観的に評価するために、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定することが不可欠です。KPIを設定することで、プロジェクトの進捗状況を定量的に測定し、万が一計画からズレが生じた場合でも迅速に軌道修正を行うことができます。例えば、「業務効率化」という目的であれば、「請求書発行業務の時間を50%削減」「月次決算の所要日数を3営業日短縮」といった具体的な数値をKPIとして設定します。
| 導入目的 | 優先度 | 具体的なKPI | 測定方法 | 目標値 |
|---|---|---|---|---|
| 経営の意思決定迅速化 | 高 | 月次決算早期化日数 | 経理部門の業務ログ | 5営業日短縮 |
| 在庫管理の最適化 | 高 | 在庫回転率 | 販売管理・在庫管理データ | 15%向上 |
| 業務プロセスの標準化 | 中 | データ二重入力の件数 | 各業務担当者へのヒアリング | 0件 |
| IT運用保守コストの削減 | 中 | 年間システム運用保守費用 | IT部門の予算実績 | 20%削減 |
ステップ4:関係者間での合意形成と共有
最後に、設定した目的、優先順位、そしてKPIを、経営層から現場の担当者に至るまで、すべての関係者(ステークホルダー)と共有し、合意を形成することがプロジェクトを円滑に進める上で極めて重要です。ERP導入は、単なるシステム刷新ではなく、業務プロセスの変革を伴う全社的なプロジェクトです。 そのため、各部門の協力なくして成功はあり得ません。
合意形成が不十分なままプロジェクトを進めると、「現場の業務実態に合わない」「導入後に使われない」といった問題が発生し、投資が無駄になるリスクがあります。以下の方法を通じて、全社的な協力体制を構築しましょう。
- プロジェクト憲章(プロジェクトチャーター)の作成:プロジェクトの目的、背景、スコープ、KPI、推進体制などを明文化し、関係者全員の目線を合わせます。
- キックオフミーティングの開催:経営トップからプロジェクトの重要性や期待する効果を直接全社に発信してもらうことで、従業員の当事者意識を高めます。
- 定期的な進捗共有会の実施:プロジェクトの進捗状況や課題を定期的に共有し、各部門からのフィードバックを収集する場を設けることで、現場の納得感を醸成します。
明確な目的を羅針盤として、全社一丸となってプロジェクトを推進することが、ERP導入を成功に導くための最も確実な道筋となるのです。
目的達成に向けたERP選定・導入の注意点
明確な目的を設定した後は、その目的を達成できるERPを正しく選定し、着実に導入プロセスを進めることがプロジェクト成功の鍵となります。しかし、多機能で高価な製品を選べば良いというわけではありません。ここでは、目的達成というゴールから逆算し、ERPの選定・導入フェーズで特に注意すべき2つのポイントを解説します。
フィット&ギャップ分析の重要性
ERP導入プロジェクトにおいて、目的達成を左右する極めて重要な工程が「フィット&ギャップ分析」です。これは、自社の業務プロセス(あるべき姿)と、導入を検討しているERPパッケージの標準機能が、どれだけ適合(フィット)し、どれだけ乖離(ギャップ)があるかを可視化・分析する手法を指します。
なぜフィット&ギャップ分析が不可欠なのか
この分析を疎かにすると、「導入したものの、現場の業務に合わず使われない」「想定外のカスタマイズが多発し、予算が大幅に超過した」といった致命的な失敗に繋がりかねません。分析を通じてギャップを正確に把握することで、そのギャップをどう埋めるか(①業務プロセスをERPに合わせる、②ERPをカスタマイズ・アドオン開発する、③運用でカバーする)という具体的な対応策を、コストや効果を天秤にかけながら合理的に判断できるようになります。
特に、ERPが持つ業界のベストプラクティス(標準的な業務プロセス)に自社の業務を合わせる(Fit to Standard)という視点は重要です。安易なカスタマイズは、将来的なバージョンアップ時のコスト増大やシステムの複雑化を招くリスクがあるため、慎重な検討が求められます。
フィット&ギャップ分析の具体的な進め方
フィット&ギャップ分析は、一般的に以下のステップで進められます。
| ステップ | 主な実施内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 要件の洗い出し | 現状の業務フローを可視化し、課題を整理した上で、新しいシステムに求める機能要件(必須要件・希望要件)を一覧化します。 | 特定の部門だけでなく、システムを利用する全部門から意見をヒアリングし、網羅的な要件を洗い出すことが重要です。 |
| 2. ERP機能との比較 | 洗い出した要件リストと、導入候補となるERP製品の標準機能を一つひとつ照らし合わせ、フィットしている(〇)か、ギャップがある(×)かを評価します。 | ベンダーにデモンストレーションを依頼し、実際の画面や操作性を確認しながら評価することで、認識のズレを防ぎます。 |
| 3. ギャップへの対応方針決定 | ギャップ(×)と評価された項目について、前述の「①業務を合わせる」「②システムを改修する」「③運用でカバーする」のいずれの方針で対応するかを決定します。 | 対応にかかるコスト、期間、導入目的への貢献度などを総合的に評価し、優先順位を付けて判断します。 |
クラウドERPという選択肢
近年、ERPの導入形態として主流になりつつあるのが、インターネット経由でサービスを利用する「クラウドERP」です。従来の自社サーバーでシステムを構築・運用する「オンプレミス型」と比較し、それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の目的やITリソースに合わせて最適な形態を選択することが重要です。
オンプレミス型との比較
クラウド型とオンプレミス型の主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | クラウドERP | オンプレミスERP |
|---|---|---|
| 初期費用 | 低い(サーバー購入などが不要) | 高い(サーバー、ライセンス購入費など) |
| 導入期間 | 短い | 長い |
| 運用・保守 | ベンダーに任せられるため、負担が少ない | 自社で専門人材を確保し、対応する必要がある |
| カスタマイズ性 | 制約がある場合が多い | 柔軟性が高い |
| セキュリティ | 専門ベンダーによる高度な対策が施されている | 自社のポリシーに合わせて自由に構築できる |
| アクセス性 | インターネット環境があればどこからでも利用可能 | 原則として社内ネットワークからのみ |
クラウドERPが選ばれる理由と注意点
クラウドERPは、初期投資を抑え、迅速に導入できる点や、法改正や機能改善のアップデートが自動で行われ、IT部門の運用保守負担を大幅に軽減できる点が高く評価されています。特に、専任のIT担当者を多く配置することが難しい中小企業や、スピーディーな事業展開を目指す成長企業にとって有力な選択肢となっています。
一方で、注意点も存在します。オンプレミス型に比べてカスタマイズの自由度が低い場合があるため、独自の業務プロセスが多い企業は、フィット&ギャップ分析をより入念に行い、標準機能で業務が遂行可能かを見極める必要があります。また、月額・年額の利用料が発生するため、長期的な視点で総所有コスト(TCO)を試算し、オンプレミス型と比較検討することが賢明です。
最終的には、どちらの形態が優れているということではなく、自社の経営戦略、事業規模、業務要件、そして最も重要な「ERP導入の目的」に立ち返り、最適な選択を行うことが成功への近道となります。
まとめ
本記事では、ERP導入における目的設定の重要性とその具体的な進め方について解説しました。ERP導入の成否は、導入そのものではなく「経営課題の解決」という明確な目的を、関係者全員で共有できるかにかかっています。システムの全体最適化を通じて、迅速な意思決定や全社的な業務効率化を実現するためにも、まずは自社の課題を洗い出し、あるべき姿を定義することから始めましょう。
- カテゴリ:
- ERP
- キーワード:
- erp導入