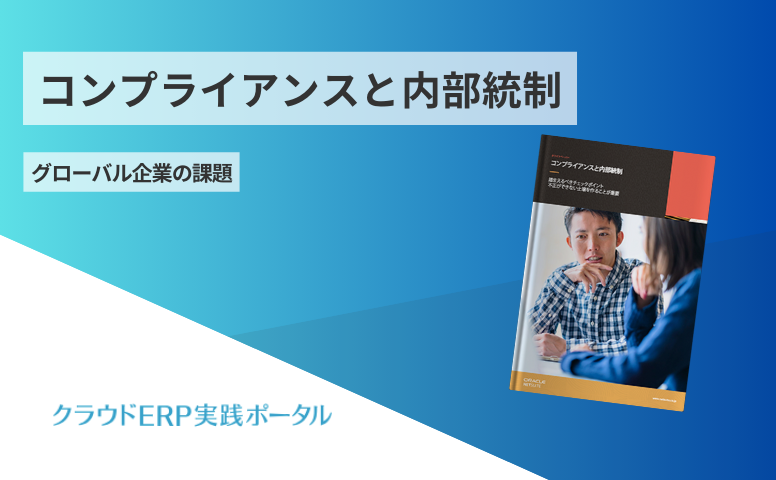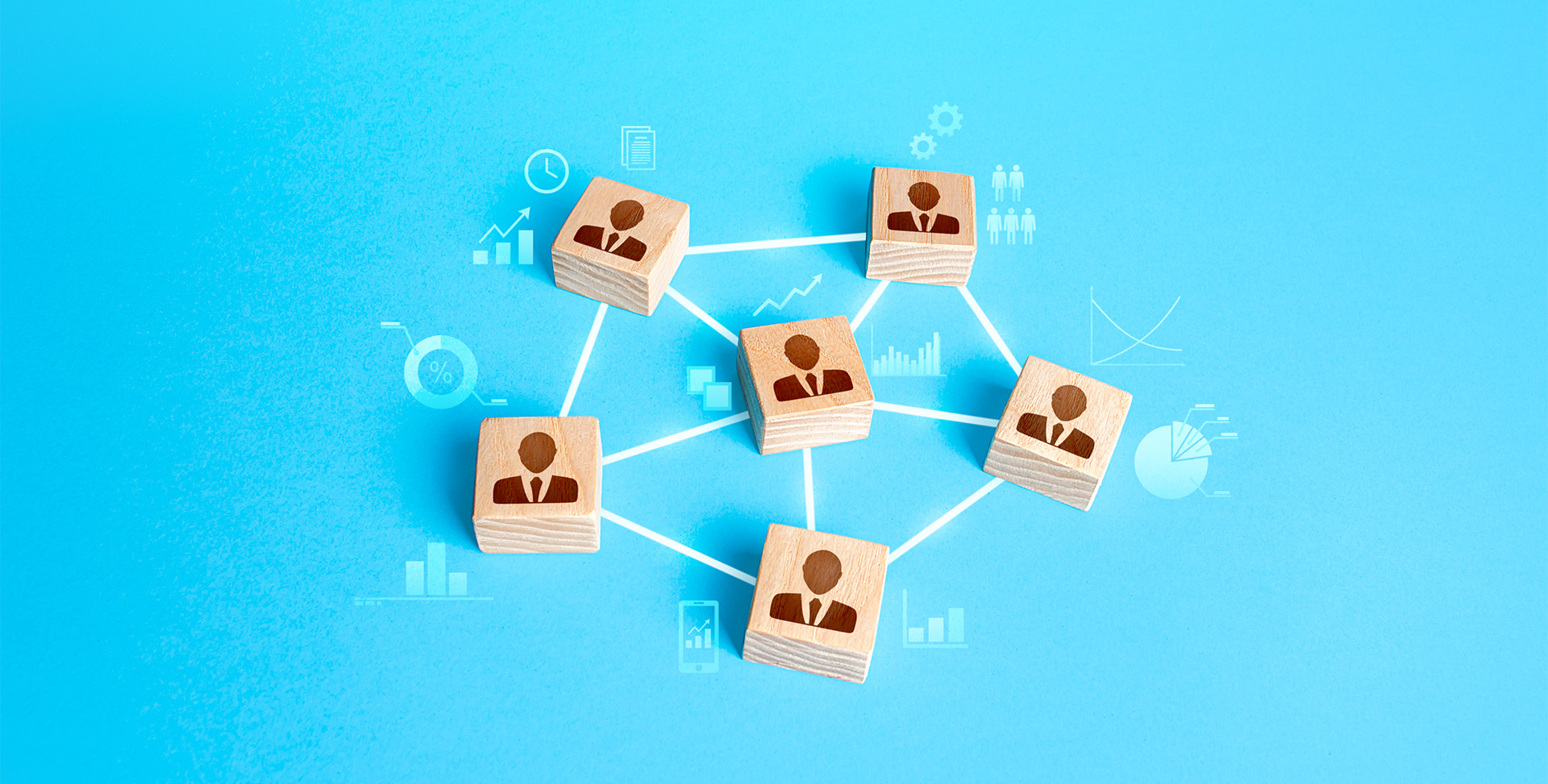コンプライアンスとは、法令・ガイドライン・社内規則・社会倫理といったルールを事業戦略に取り入れて、従業員の不正を防止し、企業の信頼維持を図ることです。本記事では、コンプライアンス違反事例と、各事例から得られる教訓を紹介します。従業員の不正・ルール違反を招く原因や企業に与える影響、リスクの軽減対策を理解し、法令遵守の経営を徹底したいと考える担当者に、参考になる内容です。

コンプライアンス違反の有名な事例一覧
コンプライアンス違反は多くの場合、以下のいずれかのカテゴリーに分類できます。
- 粉飾決算
- データ偽装
- 不正受給
- 食品衛生管理問題
- 個人情報
- 業務妨害
- ハラスメント
以下では、カテゴリーごとに有名事例を取り上げて、どのような行為がコンプライアンス違反に当たるかや、不正が起こった経緯を紹介します。自社の取り組みの参考にしてください。
1.粉飾決算
粉飾決算とは、不適切な手法を活用して決算書などを改ざんし、金融機関や取引先、投資家といった関係者に誤った情報を提供することを指します。粉飾決算が理由で倒産に至った場合には関係者を巻き込む大規模なトラブルに発展するケースも多いことから、社会に対して多大な影響を与えます。以下では、資金調達の手段として粉飾決算に手を染め、倒産にいたった2社の事例を紹介します。
堀正工業株式会社
堀正工業株式会社は、1933年創業の老舗で、大手ベアリングメーカーの代理店として成長した企業です。同社ではバブル崩壊後、一時的に業績が悪化した時期、十分な利益が出ていないことを理由に追加融資を拒否されました。2003年の社長交代後、資金調達のために粉飾決算に手を染めました。
2023年5月以降、粉飾決算が発覚したタイミングでは、最大54行の銀行に対し、異なる内容の決算書を使い分けて提示し、資金調達を行っていました。最終的に同社は不正の発覚後、約282億円以上の負債を抱えて倒産しています。
参照元:堀正工業(株) ~約50行を欺いた粉飾、明細書も細かく調整する「執念」 ~
藤崎金属株式会社
藤崎金属株式会社は、非鉄金属流通の老舗としてピーク時には50億円を超える売り上げを誇っていた企業です。同社はリーマンショック後、経済環境の変化へ対応できずに業績が低迷し、かろうじて黒字を維持していた状態でした。2015年に二代目社長の急死を受けて三代目社長が就任すると、仕入れ決算を翌期に回したり在庫の商品価値を過大評価したりする手口で粉飾決算を行っていた事実が発覚します。三代目社長の指示で経営の健全化を図ったものの、金融機関や取引先の支援は得られず、破産申立にいたりました。
株式会社てるみくらぶ
格安ツアー販売を主力事業としていた株式会社てるみくらぶでは、決算の際に約75億円もの債務超過を隠ぺいし、破産申立の直前まで営業を継続していました。同社では決算書を改ざんし、赤字を隠ぺいしていたことも判明しています。
同社の不正によって一般顧客は、すでに宿泊代金を同社へ支払っていたにもかかわらず現地で請求を受けるなどのトラブルに巻き込まれました。最終的に同社は債務の支払い見込みが立たず、2017年3月に破産手続きを開始しています。
参照元:てるみくらぶ破綻の真相が明らかに、3年前から「債務超過」と「多額の粉飾決算」、都内で債権者集会を実施
2.データ偽装
データ偽装とは、製品の品質データや食品の賞味期限などを改ざんすることを指します。データ偽装は「事実を秘匿する」といった点が粉飾決算と共通するものの、顧客の生命に関わるケースも多いことから、より深刻な問題と見なされます。
東洋ゴム工業株式会社
国土交通省は2015年、自動車タイヤの生産・販売を主力事業とする東洋ゴム工業株式会社が不正な申請書を提出し、免震ゴム製品の大臣認定を取得していたことを公表しています。対象の製品は地方自治体の庁舎や各地のマンション、病院など、全国約150棟の建築物に使用されていました。製造を担当していた子会社は、不正競争防止法違反で有罪判決を受けています。
参照元:東洋ゴム工業(株)が製造した免震材料の大臣認定不適合等について
現在の「TOYO TIRE株式会社」(旧・東洋ゴム工業株式会社)ではデータ偽装の原因は、倫理意識や規範遵守意識の欠如、内部統制体制の不備にあると解析しました。経営陣の知見不足や危機マネジメントの欠如もあって判断・対処が遅れ、問題の深刻化につながったことを認めています。
参照元:免震ゴム問題の原因について
3.不正受給
不正受給とは、虚偽の報告を行って国や地方公共団体などから補助金・支援金を受け取ることです。不正受給を行った企業の名前は国や地方公共団体のホームページで公表されるケースも多く、大幅なイメージ低下につながります。介護施設が従業員数などを水増しし、必要以上の介護報酬を受け取ることも、不正受給の一種です。
株式会社ルキオ
事業用大型プリンターの製造・販売を主力事業とする株式会社ルキオでは福島県南相馬市の工場新設時、納入業者に虚偽の書類を作成させる手口で補助金を受給しました。福島県と南相馬市は事実の発覚後、同社に対して、不正に受給した補助金の返還を命令しています。返還命令後、信用の低下で資金繰りが悪化し、事業縮小も効果を発揮せず、破産申立に至りました。
株式会社エヌ・ビー・ラボ
介護施設の運営やコンサル事業を手掛けていた株式会社エヌ・ビー・ラボでは介護報酬の水増し請求が発覚し、2016年に介護保険事業者等の指定取り消し処分を受けました。処分によって信用を失墜させた同社では運営施設をすべて他社に引き継ぎ、約14億円の負債を抱え、破産申立にいたっています。
4.食品衛生管理問題
食品衛生管理問題とは、食品衛生法に沿った衛生管理に不備があり、食中毒などを引き起こす事態のことです。食中毒などを発生させた飲食店は営業停止や廃業命令を受けるとともに、刑事上や民事上の責任を追及される可能性があります。
株式会社フーズ・フォーラス
株式会社フーズ・フォーラスは、富山県を中心に、焼肉チェーンレストランなどを20店舗展開していた企業です。2011年に同社の複数店舗でユッケなどの生肉を原因とする食中毒が起こり、5人が死亡しています。富山県から行政処分を受けた同社は全店舗の営業を自粛し、廃業にいたりました。
5.個人情報
顧客の個人情報を流出させた企業は、民事上の責任を追及されます。個人情報保護法違反が判明し、改善命令に従わない場合は、刑事罰が科される可能性もあるため、入念な対策が必要です。以下では、公的機関と民間企業で起こった個人情報流出の有名事例を紹介します。
日本年金機構
日本年金機構は、政府から委任を受け、公的年金の運営業務を担当している機関です。2015年に同機構では、業務に無関係のメールを受信した職員のうちの5人が開封し、約125万件の個人情報を流出させる事案が発生しました。
参照元:不正アクセスによる情報流出事案に関する調査結果報告について
日本年金機構の個人情報漏えいを招いたメールは「標的型攻撃メール」と呼ばれる、サイバー攻撃の一種です。警察庁によると、2024年のサイバー犯罪の検挙件数は13,164件と、前年比600件以上増加している状況であり、同機構のトラブルが対岸の火事であるとはいえません。
参照元:令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について
ソフトバンク株式会社
ソフトバンク株式会社では2023年、業務中に入手した個人情報を店舗担当者が悪用し、顧客のSNSに私的な連絡を行うトラブルが起こりました。店舗が保有する氏名、電話番号、住所などを私的に利用することは、個人情報保護法違反です。同社では連絡を行った店舗担当者が代理店のスタッフであることを認め、謝罪のコメントを公表しています。
ソフトバンク株式会社ではトラブルの再発を防止するため、代理店に対する教育を再徹底する方針です。併せて、定期的な業務の監査を実施し、コンプライアンス強化に努める方針を示しました。
参照元:ソフトバンクが謝罪 人気ユーチューバー個人情報での私的連絡「代理店スタッフが事実を認める」
6.業務妨害
社会的な倫理に反する行為を意図的に行うことも、コンプライアンス違反の一種です。近年では以下のように、コンプライアンス違反にあたる行為を撮影してSNSなどに公開するトラブルも多数発生しています。
株式会社すかいらーくホールディングス
株式会社すかいらーくホールディングスでは2024年、しゃぶしゃぶ店の従業員の公開した不適切な動画がSNSで拡散されたことを公表し、謝罪しました。拡散された動画の撮影にはアルバイト3人が関与したとされ、ホイップクリームを直接口に流し込む様子が映っていました。撮影に使用したクリームは廃棄を予定していたもので、顧客には提供されていません。
不適切な動画が一旦拡散されてしまうと、容易に削除できません。被害を防止するためには、従業員を十分に教育する、宣誓書を取り交わすなどの対処を検討する必要があります。
7.ハラスメント
ハラスメントとは、個人の尊厳を傷つけるもしくは嫌悪感を煽る言動全般です。ハラスメントは各種法令で禁止されている行為にあたり、意図的に行うことは、コンプライアンス違反にあたります。
神奈川県地域県政総合センター
神奈川県では2023年、地域県政総合センターの男性職員が女性職員に対して行った複数の発言をセクハラと認定し、減給処分を科しました。男性職員は、処分の同日付で退職しています。
参照元:女性部下に「チューしてくれたらハンコ押す」「明日から私の愛人」…県職員を減給に
神奈川県の事例は男性から女性に対する行為にあたるものの、女性から男性に対する言動も、セクハラの対象です。セクハラ以外にもさまざまな行為がハラスメントにあたり、コンプライアンス違反を回避するためには、アルコールハラスメントやパワーハラスメントも意識した対策を取る必要があります。
コンプライアンス違反が起こる原因
コンプライアンス違反の多くは、従業員の教育不足や社内体制の不備によって発生します。すべての従業員が教育を受けずとも最新の法令や規則を理解し、自覚ある行動を取れるとは限りません。どのような行為がコンプライアンス違反にあたるかを教育し、周知徹底させていない状況では、トラブルの発生リスクが高まります。
経営層が最新の法令や倫理規範を十分に理解していない場合や、法令遵守の経営に対する意識が低い場合も同様です。経営層のコンプライアンス意識が低い組織では内部統制の仕組みを構築しにくく、不正を早期に発見できない可能性があります。不正を放置するほど重大なトラブルに発展するリスクは高まり、被害を拡大させる要因となります。
コンプライアンス違反によるリスク
コンプライアンス違反が起こると企業イメージは低下し、信用を失墜します。信用を失った企業は優秀な人材を確保しにくく、市場競争力の低下につながりかねません。企業イメージが低下した状態では資金調達の難易度も上がり、株価の低下を招く可能性もあります。
コンプライアンス違反によって法令やガイドラインに反する行為を行った企業は、行政処分の対象になります。役員の管理責任が追及された場合には経営を牽引してきた人材が辞任に追い込まれ、その後の業務に支障が生じる可能性もあります。コンプライアンス違反によって顧客や従業員の生命に危険が及び、関係者から損害賠償を請求された場合には、金銭的な負担も避けられません。
コンプライアンス違反への5つの対策
コンプライアンス違反によるリスクの回避に努めるためには、以下5つのポイントを意識した対策を取りましょう。
1.経営トップの強い意志表明
法令遵守の経営を定着させるためには経営トップが率先して「コンプライアンス違反を許さない」といった意思を持ち、組織に対して表明する必要があります。経営トップの明確な意思表明を受けると、組織全体の意識改革が進むためです。意思を表明する際には、法令遵守の経営は従業員の生活と株主、企業そのものを守るために不可欠な要素であることも伝えましょう。
2.コンプライアンス専門部署(チーム)の設置
従業員に法令遵守を呼びかけても精神論の領域を越えられず、十分な成果が得られないケースは多々あります。コンプライアンス違反の告発を受け付ける組織として専門部署を立ち上げ、法令遵守の徹底を促しましょう。専門部署が告発を受けた際には従業員への聞き取り調査やエビデンスの収集を行い、状況を正しく把握した上で、社内ルールに基づく処分を検討します。
3.社内ルール策定と定期的な見直し
コンプライアンスの社内ルールがあっても、従業員が十分に理解していない場合、有効に機能しません。コンプライアンス違反を回避するためには社内ルールをあらためて見直して内容をブラッシュアップし、周知徹底してください。
また、コンプライアンスに関わる法令や規則は随時改正されていきます。社内ルールを陳腐化させないためには定期的に内容を見直し、最新の法令や規則に準拠したものへと改訂しましょう。
4.システム面でのセキュリティ強化
コンプライアンス違反を回避するには自社で採用しているITシステムの安全性を見直し、必要がある場合には、セキュリティを強化する対策も検討しましょう。たとえば、機密情報を保管しているシステムに従業員の誰もがアクセスできる状況では、情報漏えいの回避が困難です。ファイルやユーザーごとに詳細な権限を設定し、機密情報へ容易にアクセスさせない状況を整備すれば、セキュリティを強化できます。
従業員の故意による情報漏えいを防止するには、アクセスログを監視する方法も一案です。ログを監視すると、「いつ、誰が、どのデータやファイルにアクセスしたか」を逐一把握し、不審な兆候を迅速に発見できます。
5.チェックシートの活用
自社の現状を正しく把握できていない状況では、コンプライアンスとガバナンス強化のために必要な対策を見誤るリスクがあります。対策を検討する際には事前にチェックシートを活用して、現在の業務運用体制や従業員の意識などを調査しましょう。以下のページでコンプライアンスチェックシートを配布しているため、ぜひダウンロードし、現状把握に役立ててください。
まとめ
コンプライアンス違反が発生した場合に企業は、イメージの低下、売上低迷、株価の下落などの被害を受けるリスクがあります。コンプライアンス違反を回避するためには現状を正しく把握した上で、経営トップの意思表明や社内ルールの見直しと周知徹底、セキュリティ強化などの対策を取りましょう。法令遵守の経営を徹底するための第一歩は、自社の現状把握です。コンプライアンスとガバナンスの強化へ真摯に取り組み、安定的な経営を目指しましょう。
- カテゴリ:
- ガバナンス/リスク管理