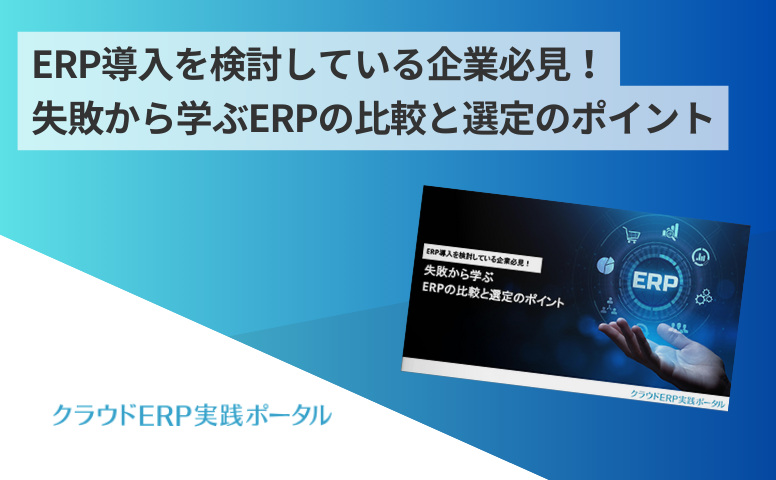「Fit to Standard」を掲げたERP導入が失敗に終わる本当の理由をご存知ですか?多くのプロジェクトが頓挫する原因は、アドオン開発の是非といった技術的な問題ではなく、経営変革への覚悟不足や旧来の業務プロセスへの固執という組織課題にあります。この記事を読めば、Fit to Standardの失敗の本質を理解し、プロジェクトを成功に導くための具体的な回避策が分かります。計画段階での目的設定から、導入時のチェンジマネジメント、運用後の効果最大化まで、各フェーズで実践すべきポイントを徹底解説。単なるシステム刷新で終わらせず、変化に強い経営基盤を構築するための道筋を描きましょう。

Fit to StandardによるERP導入が失敗に終わる本当の理由
デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の重要な一手として、多くの企業が基幹システム(ERP)の刷新に取り組んでいます。その導入アプローチとして「Fit to Standard」が主流となりつつありますが、その一方で「期待した効果が得られなかった」「プロジェクトが頓挫した」といった失敗事例が後を絶たないのも事実です。 なぜ、多くのメリットを持つはずのFit to Standardは失敗に終わってしまうのでしょうか。その原因は、ERPというシステムの技術的な側面よりも、むしろ企業の「組織」と「プロセス」に根深く潜んでいるのです。
「Fit to Standard」という言葉だけが先行していませんか?
Fit to Standardの導入が失敗する最初のつまずきは、言葉の表面的な理解に留まってしまうことにあります。 本来、Fit to StandardはERPパッケージに実装されたベストプラクティス(先進企業の優良事例)を活用し、自社の業務プロセスをグローバル標準に合わせて変革することで、経営全体の最適化を目指すアプローチです。 しかし、多くの現場では、その本質が理解されないまま、単なる「コスト削減の手法」や「カスタマイズ(アドオン開発)をしないこと」といった狭い意味で捉えられがちです。
このような誤解は、プロジェクトの目的そのものを歪めてしまいます。手段であるはずの「標準機能への適合」が目的化し、「なぜ業務を変える必要があるのか」という最も重要な議論が置き去りにされてしまうのです。 結果として、現場の納得を得られないまま強引に導入を進め、大きな抵抗を招くことになります。
Fit to Standardに対するよくある誤解と本来の目的
| よくある誤解 | 本来の目的 |
|---|---|
| 単なるコスト削減・導入期間短縮の手法 | 業務プロセスの標準化と高度化による、継続的な経営基盤の強化 |
| アドオン開発を一切行わないこと | 競争力の源泉となる領域以外は標準機能を最大限活用し、システム全体のシンプルさと保守性を維持すること |
| IT部門主導で進めるシステム刷新プロジェクト | 経営層が主導し、全部門を巻き込んで行う業務改革プロジェクト |
失敗の本質は技術ではなく組織とプロセスにある
Fit to Standardの失敗要因を深掘りしていくと、その本質が技術的な問題ではなく、人間や組織、そして既存の業務プロセスに起因する課題であることがわかります。 ERP導入は、単に古いシステムを新しいものに入れ替える作業ではありません。それは、長年慣れ親しんだ仕事の進め方、部門間の力関係、さらには企業文化そのものを変革する一大プロジェクトなのです。
最も根深い失敗原因の一つが、既存業務への固執と変化への抵抗です。 「このやり方でないと業務が回らない」「昔からこうしてきた」といった現場の声は非常に強く、新しいプロセスへの移行を阻む大きな壁となります。 特に、日本企業特有の稟議プロセスや印鑑文化、現場での「カイゼン」活動といった商習慣が、標準化の障壁となるケースも少なくありません。 これらの抵抗を乗り越えるには、経営層の強いリーダーシップと、現場の不安に寄り添う丁寧なチェンジマネジメントが不可欠です。
また、部門間の連携不足や対立もプロジェクトを停滞させる大きな要因です。各部門が自部門の業務の最適化のみを主張し、全体最適の視点が欠如してしまうと、ERPが持つ本来の力を発揮することはできません。 失敗するプロジェクトの多くは、こうした組織的な課題を軽視し、システム機能の比較検討といった技術的な側面に終始してしまう傾向があります。
【計画フェーズ】Fit to Standardの失敗を回避する準備
Fit to StandardアプローチによるERP導入プロジェクトの成否は、計画フェーズの準備がいかに周到であるかで、その8割が決まると言っても過言ではありません。多くの失敗プロジェクトは、技術的な問題以前に、この計画フェーズでの検討不足や目的設定の誤りに起因しています。 ここでは、導入プロジェクトを成功に導き、失敗の芽を早期に摘むための準備について、3つの重要なポイントを解説します。
ERP導入の目的を「業務の効率化」から「経営の変革」へ引き上げる
Fit to Standardにおける最も陥りやすい失敗の一つが、導入目的の矮小化です。 「伝票入力の手間を省きたい」「承認フローを電子化したい」といった目先の業務効率化だけをゴールに設定してしまうと、プロジェクトは必ず壁にぶつかります。なぜなら、Fit to Standardの本質は、パッケージに組み込まれたベストプラクティス(優良企業の業務プロセス)を活用し、自社の業務プロセス自体を改革することにあるからです。 現場の担当者から見れば、慣れ親しんだ業務手順の変更は、一時的に負担が増える「改悪」と映ることも少なくありません。 経営層が明確なビジョンを示さなければ、現場の抵抗に遭い、プロジェクトは迷走してしまいます。
重要なのは、ERP導入を単なるシステム刷新プロジェクトとして捉えるのではなく、経営変革を実現するための重要な経営戦略と位置づけることです。 データを一元管理し、リアルタイムに経営状況を可視化することで、迅速な意思決定を可能にする。 グローバルで統一された業務プロセスを構築し、ガバナンスを強化する。 このように、より高次の経営課題の解決を目的として設定することで、初めて全社を巻き込んだ改革へのドライブがかかるのです。
ERP導入における目的設定の比較
| よくある失敗目的(業務の効率化) | 成功に導く目的(経営の変革) |
|---|---|
| ペーパーレス化を進めたい | データドリブンな経営判断を迅速化したい |
| 二重入力をなくしたい | サプライチェーン全体の状況を可視化し、在庫を最適化したい |
| 現行システムの老朽化に対応したい | グローバル拠点の業務プロセスを標準化し、連結経営を高度化したい |
| 法改正に迅速に対応したい | 変化に強い俊敏な経営基盤を構築し、新たなビジネスモデルへの対応を可能にしたい |
自社の競争力の源泉はどこかを見極める
Fit to Standardは「システムに業務を合わせる」アプローチですが、全ての業務を思考停止で標準機能に合わせれば良いというわけではありません。計画フェーズで必ず行わなければならないのが、自社のビジネスにおける「聖域(コア領域)」と「非聖域(ノンコア領域)」を明確に定義することです。言い換えれば、自社の競争力の源泉となっている独自の業務プロセスは何かを見極める作業です。
例えば、長年の経験で培われた独自の生産計画ロジック、顧客との関係性を深化させる特殊な受注プロセス、他社に真似のできない品質管理手法などが「聖域」にあたる可能性があります。これらのコア領域は、企業の差別化要因そのものであり、安易に標準化してしまうと競争力を失いかねません。こうした領域については、標準機能に合わせるのではなく、アドオン開発や他のクラウドサービスとの連携、ローコード・プラットフォームの活用など、その独自性を維持・強化する方法を検討する必要があります。
一方で、財務会計、人事管理、購買管理といった多くの企業で共通化できるノンコア領域の業務は、積極的にERPの標準機能に合わせるべきです。これらの業務に独自のプロセスを残すことは、多くの場合「ただのこだわり」であり、コスト増やシステムの複雑化を招くだけです。どこに自社の価値の源泉があり、どこを標準化すべきか。この戦略的な切り分けを経営主導で行うことが、Fit to Standardを成功させる上で極めて重要なのです。
業務改革のグランドデザインを描けるパートナーを選ぶ
Fit to Standardの成否は、共にプロジェクトを推進するパートナー(ITベンダーやコンサルティングファーム)の選定に大きく左右されます。 単にERP製品の機能に詳しいだけのベンダーを選んでしまうと、プロジェクトは失敗に終わる可能性が高いでしょう。なぜなら、Fit to Standardは業務改革そのものであり、パートナーにはシステム構築のスキル以上に、業務と経営を深く理解し、あるべき姿(To-Beモデル)を描き出す構想力が求められるからです。
信頼できるパートナーを選定するためには、提案依頼書(RFP)の段階で、以下のような点を確認することが不可欠です。
- 業界・業種への深い知見:自社のビジネスモデルや業界特有の商習慣を理解しているか。
- Fit to Standardでの成功実績:絵に描いた餅ではなく、実際に業務改革を成功させた実績が豊富か。
- コンサルティング能力:経営層と対等に議論し、変革のグランドデザインを描けるコンサルタントが在籍しているか。
- チェンジマネジメントのノウハウ:現場の抵抗を乗り越え、新しい業務プロセスを定着させるための具体的な手法を持っているか。
- 特定製品への固執がないか:自社の課題解決のために、ERPだけでなく他のソリューションも組み合わせた最適な提案ができるか。
パートナー選定は、単なる「システム導入業者」ではなく、自社の「変革を共に推進するパートナー」を選定するという視点が不可欠です。 複数のベンダーからの提案を多角的に評価し、経営層自らが面談して、長期的に信頼関係を築ける相手を見極めることが重要です。
【導入フェーズ】プロジェクト中に発生する失敗の芽を摘む
ERP導入プロジェクトは、周到な計画を立てたとしても、実際の導入フェーズで様々な予期せぬ課題に直面します。Fit to Standardのアプローチでは、この導入フェーズでの舵取りがプロジェクトの成否を大きく左右します。ここでは、プロジェクト中に発生しがちな失敗の芽を早期に摘み取り、着実にプロジェクトを推進するための具体的なポイントを解説します。
標準機能への深い理解と徹底したギャップ分析
Fit to Standardの成功は、導入するERPパッケージの標準機能をどれだけ深く、正確に理解しているかにかかっています。「業務をシステムに合わせる」という基本方針を掲げても、その「システム」が持つポテンシャルを把握していなければ、宝の持ち腐れとなってしまいます。言葉だけが先行し、標準機能で何が実現でき、何が対応できないのかを曖昧にしたままプロジェクトを進めることが、失敗への第一歩です。
この理解度を深めるために不可欠なのが、徹底したギャップ分析(Fit & Gap分析)です。これは、自社の現行業務プロセスや将来的に目指す業務プロセスと、ERPの標準機能との間の差異を一つひとつ丁寧に洗い出し、「Fit(適合する部分)」と「Gap(乖離する部分)」を明確にしていく作業です。この分析が不十分なままでは、後工程で「こんなはずではなかった」という手戻りが多発し、プロジェクトの遅延やコスト増大、そして現場の不信感を招く直接的な原因となります。
安易なアドオン開発に逃げない判断基準を持つ
ギャップ分析を進めると、どうしても標準機能だけでは対応が難しい要件、すなわち「Gap」が見つかります。ここで現場部門から「これまでの業務のやり方を変えられない」「この機能がないと仕事にならない」といった強い要望が出てくることは珍しくありません。こうした声に押され、安易にアドオン(追加開発)やカスタマイズで対応しようとすることが、Fit to Standardにおける最も典型的な失敗パターンです。
アドオン開発は、目先の課題を解決する特効薬のように見えますが、長期的にはシステムの複雑化、バージョンアップ時の改修コスト増大、メンテナンス性の低下といった深刻な副作用をもたらします。本来Fit to Standardが目指す「システムの陳腐化防止」や「継続的な最新価値の享受」という大きなメリットを自ら手放すことになりかねません。
そこで重要になるのが、「どのような場合にアドオン開発を許可するのか」という明確な判断基準をプロジェクトの初期段階で設定し、関係者全員で合意しておくことです。感情論や声の大きさで判断するのではなく、客観的な基準に沿って冷静に要否を判断する仕組みが、プロジェクトの規律を保ちます。
アドオン開発の判断基準(例)
| 判断基準 | アドオン開発を検討するケース | 代替案を検討すべきケース |
|---|---|---|
| 競争優位性 | その業務プロセスが企業の競争力の源泉であり、他社との差別化に直結している場合。 | 社内手続きの効率化など、競争力に直接的な影響が少ない業務の場合。 |
| 法的要件・業界標準 | 日本の商習慣や法規制、業界特有の要件など、外部要因によって対応が必須となる場合。 | あくまで社内独自のルールや慣習に起因する要件の場合。 |
| 代替手段の有無 | ERPのパラメータ設定変更、運用ルールの工夫、外部ツールとの連携など、あらゆる代替案を検討してもなお実現不可能な場合。 | 業務プロセスそのものを見直す(BPR)ことで、標準機能の範囲で対応可能な場合。 |
| 投資対効果(ROI) | アドオン開発と将来にわたる保守のコストを上回る、明確で測定可能な経営的効果が見込める場合。 | 一部の担当者の利便性向上など、限定的な効果しか見込めない場合。 |
現場の不安に向き合うチェンジマネジメントの実践
Fit to StandardによるERP導入は、単なるシステムのリプレイスではありません。それは、長年慣れ親しんだ業務の進め方や役割分担、時には組織のあり方そのものを変革する一大プロジェクトです。この「変化」に対して、現場の従業員が不安や戸惑い、時には抵抗感を抱くのは当然のことです。「新しいシステムは使いこなせるだろうか」「自分の仕事はなくなってしまうのではないか」といった現場の切実な声に真摯に耳を傾けず、トップダウンで改革を押し進めようとすれば、プロジェクトは必ず壁にぶつかります。
この変化に伴う抵抗を乗り越え、変革を組織に浸透させるための体系的なアプローチが「チェンジマネジメント」です。プロジェクトを成功に導くためには、システム開発と並行して、従業員の意識変革を促すための活動を計画的かつ継続的に実践していく必要があります。
新しい業務プロセスへの移行を丁寧に支援する
チェンジマネジメントの核心は、丁寧なコミュニケーションと手厚い移行支援にあります。単に「システムがこう変わります」と一方的に通告するだけでは、現場の協力は得られません。なぜ今、業務を変える必要があるのか、新しいプロセスによって会社や自分たちの仕事がどのように良くなるのか、そのビジョンを現場の言葉で繰り返し伝えることが重要です。
具体的な支援策としては、以下のようなものが挙げられます。
- 実践的なトレーニング:単なる機能説明に終始するのではなく、実際の業務シナリオに沿って、新しいシステムでの一連の業務の流れを体験できるトレーニングを実施します。
- キーユーザーの育成:各部門から業務に精通したキーユーザーを選出し、早期にトレーニングを行うことで、彼らが部門内の指導役や相談役となれるよう支援します。
- 手厚いサポート体制:システム稼働後の一定期間は、プロジェクトメンバーやベンダーが常駐するヘルプデスクを設置するなど、問い合わせに迅速に対応できる体制を整えます。
- マニュアルやFAQの整備:誰でも参照できる分かりやすい操作マニュアルや、よくある質問とその回答をまとめたFAQサイトを用意し、自己解決を促します。
こうした地道な活動を通じて、現場の不安を一つひとつ解消し、「新しいシステムを使ってみよう」「新しい業務に挑戦してみよう」という前向きな雰囲気を醸成していくことが、円滑な移行の鍵となります。
経営層が自ら進捗を管理し意思決定を行う
Fit to Standardプロジェクトは、その影響範囲が全社に及ぶため、情報システム部門や特定の事業部門だけで完結させることは不可能です。特に導入フェーズでは、部門間の利害が対立するような、現場レベルでは解決困難な問題が必ず発生します。「A部門の業務効率を考えるとアドオンが必要だが、それを認めるとB部門との連携プロセスが複雑になる」といったケースです。
このような重要な局面において、判断をプロジェクトマネージャーや現場担当者に委ねてしまうと、部分最適の決定がなされたり、意思決定そのものが遅延したりするリスクが高まります。失敗するプロジェクトの多くは、経営層が「プロジェクトは担当者に任せてある」というスタンスで、重要な局面に関与しないという共通点があります。
プロジェクトを成功させるためには、経営層がプロジェクトの最高責任者であるという強い当事者意識を持ち、自ら進捗を管理し、重要な意思決定を迅速に行う体制が不可欠です。定期的に開催されるステアリングコミッティ(重要事項を決定する会議体)を形骸化させることなく、プロジェクトの課題やリスクをリアルタイムに把握し、全社最適の視点から最終的な判断を下す。この経営層の強いリーダーシップとコミットメントこそが、部門間の壁を乗り越え、プロジェクトを正しい方向へと導く最大の推進力となるのです。
【導入後】Fit to Standardの効果を最大化する運用のポイント
ERPの導入プロジェクトは、システムが稼働した瞬間がゴールではありません。むしろ、そこからがFit to Standardアプローチの真価が問われるスタートラインです。導入後の運用フェーズでつまずき、「結局、前のシステムと変わらない」「期待した効果が得られない」といった失敗に陥るケースは少なくありません。この章では、導入したシステムの効果を最大化し、継続的な成長の基盤とするための運用のポイントを具体的に解説します。
継続的な業務改善と効果測定のサイクルを回す
Fit to Standardで導入したERPは、いわば「標準化された業務プロセスの器」です。この器を最大限に活用し、ビジネスの成長に合わせて進化させていくためには、導入効果を定量的に測定し、継続的な改善サイクルを確立することが不可欠です。場当たり的な改善ではなく、データに基づいたPDCAサイクルを組織的に回していく仕組みを構築しましょう。
まず、計画フェーズで設定したKPI(重要業績評価指標)の達成度を定期的にモニタリングします。ERPから収集されるデータを活用し、ダッシュボードなどで効果を可視化することで、経営層から現場の担当者までが共通の指標で状況を把握できるようになります。
効果測定におけるKPIの測定項目例
| 領域 | KPI項目 | 測定内容 |
|---|---|---|
| 財務・会計 | 月次決算早期化 | 決算にかかる日数が目標通り短縮されているか |
| 販売・在庫 | 在庫回転日数 | 過剰在庫が削減され、キャッシュフローが改善しているか |
| 生産・製造 | 生産リードタイム | 受注から出荷までの期間が短縮されているか |
| 業務効率 | 手作業によるデータ入力時間 | システム化により手作業が削減され、生産性が向上しているか |
これらのKPIを測定するだけでなく、その結果を分析し、次のアクションにつなげることが重要です。例えば、「在庫回転日数が目標に達していない」のであれば、その原因が需要予測の精度にあるのか、発注プロセスにあるのかを深掘りし、ERPの機能を活用した改善策を立案・実行します。現場からのフィードバックを吸い上げる仕組みを設け、「システムを使いこなす」から「システムで業務を改善する」という文化を醸成していくことが、Fit to Standardの成功を持続させる鍵となります。
システムの陳腐化を防ぎ常に最新の価値を享受する
Fit to Standardアプローチの大きなメリットの一つは、システムの陳腐化を防ぎやすい点にあります。特に、SAP S/4HANA CloudやOracle NetSuite、Microsoft Dynamics 365といったクラウドERP(SaaS型ERP)を導入した場合、ベンダーによって四半期や半期に一度の頻度で定期的なアップデートが行われます。
このアップデートには、最新のテクノロジー(AI、機械学習など)を取り入れた新機能の追加や、法改正への対応、セキュリティの強化などが含まれており、企業は自社で大規模な開発を行うことなく、常に最新のシステム環境を享受できます。アドオン開発を最小限に抑えているため、アップデートに伴う影響調査や改修のコストと時間を大幅に削減できるのです。
しかし、この恩恵を最大限に受けるためには、受け身の姿勢ではいけません。ベンダーから提供されるアップデート情報を主体的に収集し、追加される新機能が自社のどの業務課題の解決に貢献するのかを検討するプロセスが不可欠です。
例えば、AIを活用した需要予測機能が追加されたのであれば、それを活用して在庫最適化の精度をさらに高められないか、といった検討を行います。新機能の活用方法について社内での勉強会を実施したり、業務プロセスへの組み込みを計画的に進めたりすることで、システムへの投資対効果(ROI)を継続的に高めていくことができます。アップデートを単なる「システムのメンテナンス」と捉えるのではなく、「自社の競争力を強化するための絶好の機会」と捉えるマインドセットが、導入後の成否を大きく左右するのです。
Fit to Standardの成功が導く未来 経営プラットフォームの構築
Fit to StandardアプローチによるERP導入の成功は、単なるシステム刷新という短期的な目標達成に留まりません。それは、企業の競争力を根底から支える、持続可能な「経営プラットフォーム」を構築することに他ならないのです。 アドオン開発を最小限に抑制し、ERPが提供する世界のベストプラクティスを業務プロセスの標準とすることで、企業はこれまでの課題から解放され、新たな成長ステージへと進むための強固な基盤を手に入れます。 このプラットフォームは、変化の激しい時代を勝ち抜くための羅針盤であり、新たな価値を創造するためのエンジンとなります。
変化に強い俊敏な経営基盤
現代のビジネス環境は、市場の変動、法改正、地政学リスクなど、予測不可能な要素に満ちています。このような環境下で企業が持続的に成長するためには、変化に迅速かつ柔軟に対応できる「俊敏性(アジリティ)」が不可欠です。Fit to Standardで構築された経営基盤は、まさにこの俊敏性を企業にもたらします。
従来のFit & Gapアプローチで多用されたアドオン開発は、一時的な業務効率化と引き換えに、システムの複雑化やブラックボックス化を招き、将来のバージョンアップや法改正への対応を困難にする足枷となっていました。 しかし、Fit to StandardによってコアとなるERPをクリーンに保つことで、システムが陳腐化するリスクを低減し、常に最新のテクノロジーや機能の恩恵を享受できる状態を維持します。 例えば、海外拠点への進出やM&Aによる事業統合の際も、グローバルで標準化された業務プロセスを迅速に展開することが可能になります。
従来のアプローチとFit to Standardによる経営基盤の違い
| 比較項目 | 従来のアプローチ(Fit & Gap) | Fit to Standardアプローチ |
|---|---|---|
| ビジネス環境の変化への対応 | アドオンの改修に多大なコストと時間が必要となり、対応が後手に回りがち。 | ERPベンダーが提供する更新プログラムの適用で迅速に対応可能。事業再編にも柔軟に対応できる。 |
| システムの保守・運用 | アドオン部分がブラックボックス化し、保守コストが増大。属人化のリスクも高い。 | シンプルなシステム構成により保守性が向上。 運用負荷とTCO(総所有コスト)を大幅に削減。 |
| ガバナンス・内部統制 | 拠点や部門ごとにプロセスが異なり、全社統一のガバナンス徹底が困難。 | 業務プロセスの標準化により、全社的なガバナンスと内部統制を強化。 |
| グローバル展開 | 各拠点での個別最適化が進み、本社からの経営状況の把握が困難。 | 統一された業務プロセスとデータ基盤により、グローバルレベルでの経営の可視化と迅速な意思決定を実現。 |
全社データ活用による新たな価値創造
Fit to Standardのもう一つの大きな価値は、これまで部門ごとにサイロ化されていた経営データを全社横断で統合し、データドリブン経営を実現する基盤を構築できる点にあります。 業務プロセスが標準化されることで、データの定義や粒度も統一され、信頼性の高いデータがERPに蓄積されていきます。 この統合されたデータを活用することで、企業は新たな価値を創造することが可能になります。
例えば、販売、生産、在庫、会計といったデータをリアルタイムに連携・分析することで、以下のような価値創造が期待できます。
- 精度の高い需要予測と在庫最適化:リアルタイムの販売実績と在庫データを分析し、機械学習などを活用して需要を予測。過剰在庫や欠品リスクを最小限に抑え、キャッシュフローを改善します。
- 収益性の多角的な分析:製品別、顧客別、地域別など、様々な切り口で収益性を可視化。 どの分野に経営資源を集中すべきか、データに基づいた的確な判断が可能になります。
- 新たなサービス・ビジネスモデルの創出:蓄積された購買データや顧客行動データを分析し、新たなサービスの開発やパーソナライズされたマーケティング施策の立案につなげます。
- 従業員の生産性向上:AIを活用した定型業務の自動化機能などを活用することで、従業員はより付加価値の高い戦略的な業務に集中できるようになります。
Fit to Standardの成功は、単にERPという「守り」のIT投資を最適化するだけではありません。それは、データを活用してビジネスを成長させる「攻め」のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための経営プラットフォームを手に入れることを意味します。 この強固な基盤の上でこそ、企業は持続的な成長と競争優位性の確立を実現できるのです。
まとめ
Fit to StandardによるERP導入の失敗は、技術的な問題ではなく、組織やプロセスの変革への準備不足に起因します。成功の鍵は、導入目的を単なる業務効率化から「経営の変革」へと引き上げることです。計画段階で自社の競争力の源泉を見極め、導入中は安易なカスタマイズを避け、現場の抵抗に向き合うチェンジマネジメントと経営層の強いリーダーシップが不可欠です。これらを実行することで、変化に強い経営基盤を構築し、持続的な成長を実現できるでしょう。
- キーワード:
- DX