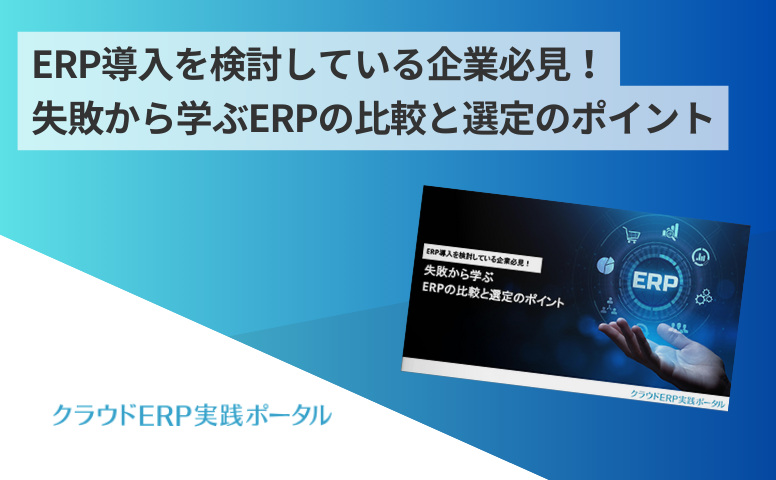ERP導入で主流となりつつある「Fit to standard」。しかし、「具体的な進め方がわからない」「従来手法との違いは?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。本記事では、Fit to standardの基本的な考え方から、準備・実行・定着化という各フェーズにおける具体的な進め方を徹底解説します。成功の鍵は、現状の業務プロセスに固執せず、ERPの標準機能に業務を合わせるという経営層と現場の強い意志です。この記事を読めば、プロジェクトを成功に導くための5つの重要ポイントと、導入後の未来像まで理解でき、明日からのアクションプランが明確になります。

Fit to standardとは 基礎からわかるERP導入の新常識
近年、ERP(Enterprise Resource Planning)をはじめとする基幹システムの導入において、「Fit to standard(フィット・トゥ・スタンダード)」というアプローチが新たな常識となりつつあります。 これは、変化の激しいビジネス環境へ迅速に対応し、DX(デジタルトランスフォーメーション)を成功させるための重要な鍵とされています。この章では、Fit to standardの基本的な考え方と、従来の手法との違いを詳しく解説します。
Fit to standardの基本的な考え方
Fit to standardとは、その名の通り「標準(Standard)に適合させる(Fit)」という考え方です。 具体的には、ERPパッケージなどが提供する標準機能に、自社の業務プロセスを合わせていく導入手法を指します。 これまでのシステム導入では、自社の業務に合わせてシステムを改修(カスタマイズ)することが一般的でしたが、Fit to standardではその逆の発想をとります。 つまり、システムのカスタマイズやアドオン開発を可能な限り行わず、パッケージに組み込まれている先進企業の優良事例(ベストプラクティス)を集約した業務プロセスを最大限に活用することを目指すアプローチです。 この手法は、特にSaaS型やクラウド型のERPが普及する中で主流となりつつあります。
この考え方が注目される背景には、従来の開発手法が招いたシステムの複雑化、高コスト化、そして硬直化といった課題があります。 過度なカスタマイズは「技術的負債」となり、バージョンアップへの追随を困難にし、結果として企業の競争力を削ぐ原因となっていました。 Fit to standardは、こうした課題を解決し、システム導入を単なるITプロジェクトではなく、業務改革を伴う経営変革の機会として捉える点で、現代のビジネス環境に適したアプローチと言えます。
従来手法(Fit and Gap)との決定的な違い
Fit to standardと比較される従来の手法が「Fit and Gap(フィット・アンド・ギャップ)」です。 Fit and Gapは、まず自社の現行業務プロセスを正とし、導入するERPパッケージの標準機能と比較します。 そして、適合する部分(Fit)と乖離している部分(Gap)を洗い出し、そのギャップを埋めるためにシステムのカスタマイズやアドオン開発を行うのが特徴です。 これは「業務内容にシステムを合わせる」アプローチと言えます。
両者の違いは、どちらを主軸に置くかという点にあります。Fit to standardが「システム」を主軸に業務を変革するトップダウン型のアプローチであるのに対し、Fit and Gapは「自社の現行業務」を主軸にシステムを調整するボトムアップ型のアプローチです。 以下の表で、両者の決定的な違いを整理します。
| 比較項目 | Fit to standard | Fit and Gap(従来手法) |
|---|---|---|
| 基本的な考え方 | システムの標準機能に、自社の業務プロセスを合わせる | 自社の業務プロセスに、システムを合わせる |
| カスタマイズ・アドオン | 原則行わない(最小限に抑制) | ギャップを埋めるために積極的に行う |
| 主導 | 経営層が主導するトップダウンでの業務改革 | 現場部門の意見を重視するボトムアップでの改善 |
| 導入期間 | 短期 | 長期化しやすい |
| 導入・運用コスト | 比較的低い(TCOを最適化) | 高額になりやすい |
| 保守・拡張性 | 高い(バージョンアップが容易) | 低い(システムのブラックボックス化、属人化のリスク) |
| 導入のゴール | 業務プロセスの標準化と継続的な業務改革 | 現行業務の維持とシステムへの置き換え |
ただし、Fit to standardはカスタマイズを完全に禁止するものではありません。 企業の競争力の源泉となるような、真に差別化が必要な業務領域においては、ERP本体に手を加えるのではなく、外部サービスとの連携やノーコード・ローコードツールなどを活用して機能を補完するアプローチが推奨されます。 これにより、ERPのコア部分をクリーンに保ちながら、ビジネスの要求に柔軟に対応することが可能になります。
Fit to standardという進め方を選ぶべき3つの理由
DX推進が叫ばれ、市場の不確実性が増す現代において、ERP導入の進め方として「Fit to standard」が新たな常識となりつつあります。 従来のFit and Gap手法が抱えていた課題を克服し、企業の持続的な成長を支える経営基盤を構築するために、なぜ今Fit to standardが選ばれるのか。その具体的な3つの理由を解説します。
理由1 変化に強いシステム基盤を構築できる
今日のビジネス環境は、法改正、新しいビジネスモデルの台頭、M&Aによる組織再編など、予測困難な変化に常にさらされています。このような環境下で企業が競争力を維持し続けるためには、変化に迅速かつ柔軟に対応できるシステム基盤が不可欠です。
Fit to standardは、ERPパッケージの標準機能を最大限に活用し、アドオン開発などのカスタマイズを最小限に抑えるアプローチです。 これにより、システムが特定の業務プロセスに過度に最適化され、複雑化・ブラックボックス化してしまう「技術的負債」を防ぎます。 結果として、ERPの定期的なバージョンアップにも迅速に対応でき、常に最新のテクノロジーやセキュリティを享受することが可能になります。 特に、機能改善が頻繁に行われるクラウドERP(SaaS)のメリットを最大限に引き出すためには、Fit to standardのアプローチが極めて有効です。
理由2 TCO(総所有コスト)を最適化できる
システム導入において、初期の開発コストだけでなく、導入後の運用・保守、将来のアップグレードまで含めた総所有コスト(TCO)の視点は欠かせません。 従来のFit and Gapアプローチでは、要件に合わせて大規模なアドオン開発を行うため初期コストが増大し、さらにその後の保守やバージョンアップの際にも多大な追加コストが発生する傾向がありました。
Fit to standardでは、アドオン開発を抑制することで、初期の開発コストと将来にわたる保守・運用コストの両方を大幅に削減します。 システムの構造がシンプルに保たれるため、運用保守業務が属人化しにくく、安定したシステム稼働が実現できます。 Fit and GapとFit to standardのコスト構造の違いは、以下の表のように整理できます。
| コスト項目 | 従来手法(Fit and Gap) | Fit to standard |
|---|---|---|
| 初期開発コスト | 業務要件に合わせた大規模なアドオン開発により高額化しやすい。 | アドオン開発を最小限に抑えるため、低コストでの導入が可能。 |
| 保守・運用コスト | 独自開発部分の保守や、属人化した運用によりコストが増大する。 | 標準機能中心のため保守が容易。ベンダーサポートを活用できコストを抑制。 |
| バージョンアップコスト | アドオン部分が原因で、バージョンアップの度に大規模な改修と追加コストが発生。 | 標準機能の範囲内であれば、低コストかつスムーズな適用が可能。 |
| 総所有コスト(TCO) | 初期・運用・将来コストのすべてが高止まりする傾向。 | 導入から運用、将来の更新までトータルでのコスト最適化を実現。 |
理由3 先進企業の業務プロセス(ベストプラクティス)を取り込める
Oracle NetSuiteといった現代のERPパッケージには、世界中の先進企業の成功事例に基づき、最適化・標準化された業務プロセス、すなわち「ベストプラクティス」が標準機能として組み込まれています。
Fit to standardは、自社の業務をシステムの標準機能に合わせて見直すことで、これらのベストプラクティスを自社に取り込み、業務改革(BPR)を強力に推進するアプローチです。 これまで慣習的に行われてきた非効率な業務や、特定の担当者にしか分からない属人化したプロセスを排除し、全社レベルでの業務標準化を実現します。 これにより、内部統制の強化、生産性の向上、そしてデータに基づいた迅速な経営判断が可能となり、単なるシステム刷新に留まらない、企業全体の競争力強化へと繋がるのです。
完全ガイド Fit to standardの進め方をフェーズごとに徹底解説
Fit to standardアプローチによるERP導入プロジェクトは、単なるシステム刷新に留まらず、業務改革を伴う一大プロジェクトです。成功のためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠となります。ここでは、プロジェクトを「準備」「実行」「定着化」の3つの主要フェーズに分け、各段階で実施すべき具体的なタスクと成功のポイントを詳細に解説します。
準備フェーズ プロジェクトの目的と体制を固める
準備フェーズは、プロジェクト全体の方向性を決定し、成功の土台を築く最も重要な期間です。ここでの決定が、後続のフェーズに大きな影響を与えます。
経営層と現場を巻き込んだ目的の合意形成
Fit to standardの推進には、業務プロセスの変更など、現場の痛みを伴う意思決定が不可欠です。そのため、プロジェクトの初期段階で「なぜERPを導入するのか」「導入によって何を実現したいのか」という目的を、経営層から現場の従業員まで、全社的に共有し、合意を形成することが極めて重要になります。 目的が曖昧なままプロジェクトを進めると、部門間の対立や現場の抵抗を招き、プロジェクトが頓挫する原因となりかねません。目的を明確にすることで、プロジェクトは推進力を得て、困難な意思決定の場面でも立ち返るべき指針となります。
具体的には、以下のような項目について具体的な目標(KPI)を設定し、合意を形成します。
- 経営データのリアルタイム可視化による意思決定の迅速化
- 業務プロセスの標準化による生産性向上とコスト削減
- 属人化の解消と内部統制の強化
- 市場の変化に迅速に対応できる柔軟な経営基盤の構築
プロジェクトチームの組成と役割分担
プロジェクトを円滑に推進するためには、各部門から適切な人材を選出し、それぞれの役割と責任を明確にした専門チームを組成する必要があります。 Fit to standardはトップダウンの意思決定と現場の主体的な参画の両輪が不可欠なため、バランスの取れたチーム編成が求められます。
プロジェクトチームの役割分担(例)
| 役割 | 主な担当者 | 主な責任・タスク |
|---|---|---|
| プロジェクトオーナー | 経営層(役員クラス) | プロジェクト全体の最高意思決定、経営視点での方針提示、予算承認、部門間の利害調整 |
| プロジェクトマネージャー(PM) | 情報システム部門長、経営企画部長など | プロジェクト全体の進捗管理、課題管理、リスク管理、ベンダーコントロール、チーム内の調整 |
| 業務プロセスオーナー | 各業務部門の部長・課長クラス | 担当業務領域における新プロセスの設計、部門内の意見集約と調整、改革の推進 |
| キーユーザー | 各業務部門のエース級社員 | ERP標準機能の理解、新業務プロセスの詳細検討、現場への展開、ユーザーテストの主導 |
| IT担当者 | 情報システム部門の担当者 | システム設定(パラメータ設定)、データ移行計画の策定・実行、技術的な課題への対応 |
実行フェーズ 業務改革とシステム導入を推進する
実行フェーズでは、準備フェーズで定めた方針に基づき、具体的な業務改革とシステムの導入作業を並行して進めます。Fit to standardアプローチの核心部分であり、業務部門とIT部門の密な連携が成功の鍵を握ります。
ERP標準機能のインプットとワークショップ
従来のFit and Gapと異なり、Fit to standardではまずERPパッケージにどのような標準機能(ベストプラクティス)が備わっているかを徹底的に理解することから始めます。 導入パートナーの支援を受けながら、会計、販売、購買、生産といった各業務領域の標準プロセスについて、デモンストレーションを交えたインプットセッションを実施します。
その上で、キーユーザーを中心にワークショップを開催し、「この標準機能を使えば、自社の業務はどのように変わるのか」「どうすれば標準機能に合わせて業務を遂行できるか」を徹底的に議論します。ここでは、現状の業務プロセスに固執せず、ゼロベースで理想の業務プロセスを考える姿勢が重要です。
新業務プロセスの設計とギャップの吸収方法の検討
ワークショップでの議論を経て、ERPの標準機能に合わせた新しい業務プロセス(To-Beモデル)を設計します。しかし、企業の競争力の源泉となっている独自のプロセスなど、どうしても標準機能だけでは対応できない「ギャップ」が明らかになることもあります。
重要なのは、ギャップが発見された際に、安易にカスタマイズ(アドオン開発)を選択しないことです。 まずは業務プロセスの変更や運用での工夫によってギャップを吸収できないかを最優先で検討します。アドオン開発は、プロジェクトの遅延やコスト増加、将来のアップグレード時の障害となるため、最終手段と位置づけるべきです。
ギャップの吸収方法と優先順位
| 優先度 | 吸収方法 | 具体例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高 | 業務プロセスを変更する | システムの承認フローに合わせて、社内の稟議規程を見直す | 最も推奨されるFit to standardの基本的な考え方 |
| 中 | 運用でカバーする | 帳票のレイアウト変更は行わず、Excelなどを使って手動で補足資料を作成する | RPA(Robotic Process Automation)の活用も有効な選択肢 |
| 低 | パラメータ設定で対応する | 消費税率の変更など、システムの設定変更で対応する | システムの標準機能の範囲内での対応 |
| 最終手段 | アドオン開発・外部連携 | 業界特有の取引形態など、競争力維持に不可欠な機能のみ追加開発する。または外部サービスと連携する | 費用対効果を厳密に評価し、経営層の承認を得ることが必須 |
定着化フェーズ 導入効果を最大化する
システムを導入して終わりではありません。新しい業務プロセスとシステムを全従業員が使いこなし、導入効果を継続的に創出し続けるための「定着化」が最後の重要なフェーズです。
ユーザーへのトレーニングとマニュアル整備
新しい業務プロセスへの移行をスムーズに行うため、全部門の利用者を対象としたトレーニングを実施します。 役職や役割に応じてトレーニング内容を設計し、システムの操作方法だけでなく、「なぜ業務プロセスが変わったのか」という背景や目的も丁寧に説明することが、ユーザーの納得感を得る上で重要です。 また、いつでも業務手順を確認できるオンラインマニュアルやFAQサイトを整備し、導入後の問い合わせに対応するヘルプデスク体制を構築することも、定着化を促進します。
効果測定と継続的な改善活動
導入後は、準備フェーズで設定したKPIを基に、定期的に導入効果を測定・評価します。 「業務処理時間は短縮されたか」「データ入力のミスは削減されたか」といった具体的な指標で効果を可視化し、経営層や関係者に報告します。
ERPは導入がゴールではなく、企業の成長を支える経営基盤です。効果測定の結果から新たな課題を発見し、さらなる業務改善やシステムの活用方法を検討する、といった継続的な改善活動(PDCAサイクル)を回していくことが、投資対効果を最大化する上で不可欠です。
Fit to standardの成否を分ける5つの成功ポイント
Fit to standardアプローチは、正しく進めればERP導入の期間短縮やコスト削減に大きく貢献します。しかし、その過程にはいくつかの落とし穴も存在します。ここでは、プロジェクトを成功に導くために不可欠な5つの重要ポイントを、具体的なアクションと共に解説します。
ポイント1 経営層の強いリーダーシップと覚悟
Fit to standardは、単なるシステム導入プロジェクトではありません。既存の業務プロセスを抜本的に見直し、全社的な変革を断行する経営改革そのものです。 そのため、プロジェクトの成否は経営層のコミットメントに大きく左右されます。 現場からは、慣れ親しんだ既存業務の継続を求める声や、変化に対する抵抗が必ず生じます。 こうした声に押し切られ、安易なカスタマイズを許容してしまっては、Fit to standardのメリットは失われてしまいます。
経営層には、なぜ今この改革が必要なのか、その目的とビジョンを自らの言葉で繰り返し発信し、全社に浸透させることが求められます。 そして、時には非情とも思える「標準機能に合わせる」という意思決定を迅速に行う覚悟が必要です。 経営層が「改革の最後の砦」として機能することで、プロジェクトは推進力を得て前進することができます。
ポイント2 業務部門の主体的なプロジェクト参画
新しい業務プロセスを設計し、日々それを利用するのは情報システム部門ではなく、現場の業務部門です。業務部門が「自分たちの改革」として当事者意識を持てるかどうかが、導入後のシステム定着を大きく左右します。 プロジェクトをITベンダーや情報システム部門に任せきりにするのではなく、企画の初期段階から各業務のキーパーソンを巻き込み、主体的に関与してもらう体制を構築することが不可欠です。
具体的には、以下のような役割を担ってもらうことが重要です。
| 役割 | 具体的な活動内容 |
|---|---|
| 変革の推進者(チェンジリーダー) | ERPの標準機能を深く理解し、そのメリットを自部門のメンバーに説明する。新しい業務プロセスへの移行をリードし、現場の疑問や不安を解消する。 |
| 新業務プロセスの設計者 | ワークショップに積極的に参加し、ERPの標準機能を前提とした新しい業務フローの設計に主体的に関わる。 |
| 教育・トレーニングの担い手 | 導入後のユーザー向けトレーニングにおいて、講師やサポーターとして協力し、新システムの定着を支援する。 |
業務部門の参画度を高めることは、通常業務との両立など負担を強いる側面もありますが、ここでの投資が将来の定着化と活用度向上に繋がり、結果として大きなリターンをもたらします。
ポイント3 現状維持バイアスを乗り越える工夫
人間は本能的に変化を嫌い、現状を維持しようとする「現状維持バイアス」を持っています。Fit to standardプロジェクトにおいて、「今までのやり方で問題なかった」「なぜ変える必要があるのか」といった抵抗勢力は必ず現れます。 この心理的な壁を乗り越えるためには、丁寧なコミュニケーションと計画的な「チェンジマネジメント」が極めて重要です。
単に「システムがこうなるから業務を変えろ」というトップダウンの指示だけでは、現場の反発を招くだけです。新しい業務プロセスがもたらす具体的なメリットを、データを用いて定量的に示すことが効果的です。
| 変革への抵抗(例) | 乗り越えるためのアプローチ(例) |
|---|---|
| 「独自の帳票フォーマットは取引先との約束であり、変更できない」 | 標準帳票で出力した上で、RPAなどを活用して取引先指定フォーマットへ変換する代替案を検討し、手作業の削減効果を提示する。 |
| 「新しい操作を覚えるのが大変だ」 | 直感的に操作できるデモを見せたり、十分なトレーニング期間と手厚いサポート体制を約束したりすることで、移行への不安を払拭する。 |
| 「標準機能では、自社の強みである独自の業務プロセスが実現できない」 | 本当に競争力の源泉となっている業務なのかを客観的に分析し、標準化による効率化のメリットと比較検討する場を設ける。 |
変革には痛みが伴うことを率直に認めつつも、それを乗り越えた先にあるメリットを共有し、ポジティブな未来像を描くことで、現状維持バイアスを乗り越える原動力を生み出します。
ポイント4 経験豊富な導入パートナーを見極める
Fit to standardの経験が豊富な導入パートナーの選定は、プロジェクトの成功を左右する最も重要な要素の一つと言っても過言ではありません。 パートナーの役割は、単にシステムを構築することだけではありません。ERPの標準機能と業界のベストプラクティスに精通し、企業の業務改革をリードする「伴走者」としての役割が求められます。
パートナー選定の際には、以下の点を見極めることが重要です。
-
Fit to standardアプローチでの導入実績: 自社と同業種・同規模の企業への導入実績が豊富か。成功事例だけでなく、過去の失敗から得た教訓についても尋ねると良いでしょう。
-
業務改革のコンサルティング能力: 現場の抵抗に直面した際に、粘り強く説得し、合意形成を導くための方法論やスキルを持っているか。
-
チェンジマネジメントの知見: ユーザーの不安を払拭し、新しいシステムへの移行をスムーズに進めるためのトレーニングやコミュニケーション計画に関するノウハウを持っているか。
-
「No」と言える姿勢: 企業の要求に対して、それがFit to standardの原則から外れるものであれば、安易に受け入れるのではなく、代替案を提示しながらも「できない」とはっきり言える誠実さがあるか。
提案内容や費用だけでなく、担当コンサルタントの経験や人柄、自社との相性も慎重に評価し、信頼できるパートナーを選ぶことが成功への近道です。
ポイント5 導入後の活用を見据えたKPI設定
ERPの導入は、本番稼働がゴールではありません。導入したシステムをいかに活用し、ビジネス上の成果に繋げるかという視点が不可欠です。 そのためには、プロジェクトの構想段階で、導入後の「あるべき姿」を定義し、その達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)を具体的に設定しておくことが重要です。
KPIを設定することで、プロジェクトの目的が明確になり、関係者の意識を統一する効果があります。 また、導入後も定期的にKPIを測定・評価することで、効果を可視化し、継続的な改善活動へと繋げることができます。
| 領域 | KPI設定例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 財務会計 | 月次決算の早期化(例: 10営業日 → 5営業日) | 経営判断の迅速化 |
| 販売管理 | 受注から出荷までのリードタイム短縮(例: 20%削減) | 顧客満足度の向上 |
| 在庫管理 | 在庫回転率の向上(例: 15%向上) | キャッシュフローの改善 |
| 全社共通 | 手作業によるデータ集計・転記時間の削減(例: 50%削減) | 生産性の向上、高付加価値業務へのシフト |
設定するKPIは、「売上向上」のような漠然としたものではなく、上記のように具体的で測定可能な指標であることがポイントです。Fit to standardの導入効果を最大化するために、導入後の活用と改善のサイクルを計画に組み込んでおきましょう。
Fit to standardの先にある未来 経営プラットフォームとしてのERP
Fit to standardというアプローチは、単なるシステム導入手法に留まりません。これは、企業の根幹を成す業務プロセスをグローバル標準のベストプラクティスに合わせ、変化の激しい時代を勝ち抜くための強固な「経営プラットフォーム」を構築するという、未来に向けた経営戦略そのものです。 システムが業務の足かせとなる時代は終わり、ビジネスの成長を加速させるエンジンへと変貌を遂げるのです。
リアルタイム経営による市場変化への即応
Fit to standardで導入されたクラウドERPは、これまで部門ごとにサイロ化されがちだった販売、生産、会計といった基幹業務のデータをリアルタイムで統合します。 これにより、経営層は常に最新かつ正確な情報に基づいた意思決定を行えるようになり、「勘と経験」に頼った経営から脱却し、データドリブン経営(データに基づいた客観的な経営)へと大きく舵を切ることが可能になります。
例えば、経営ダッシュボードを開けば、全社の受注状況、工場の生産進捗、各製品の在庫レベル、そして資金繰りの状況までが一目で可視化されます。 市場の需要が急に変動した場合でも、その影響を即座に把握し、生産計画の調整や販売戦略の見直しといった次の一手を迅速に打つことができるのです。 まさに、ビジネスの「今」を正確に捉え、未来を予測する羅針盤を手に入れることに他なりません。
| 項目 | 従来型(Fit and Gap)の課題 | Fit to standardがもたらす未来 |
|---|---|---|
| データ連携 | 部門最適化されたシステムが乱立し、データが分断。バッチ処理などで連携するためタイムラグが発生。 | 単一のプラットフォームにデータが統合され、リアルタイムでの情報共有が実現。 |
| 意思決定 | 情報の収集と集計に時間がかかり、意思決定が遅れがち。過去のデータに基づく判断が中心。 | 常に最新のKPIをダッシュボードで確認し、迅速かつ正確な意思決定が可能に。 |
| 市場対応 | 市場や顧客ニーズの変化に対する感度が低く、後手に回ることが多い。 | データ分析に基づき変化の兆候を早期に察知し、プロアクティブな対応が可能。 |
継続的なビジネスモデル変革を支える基盤
Fit to standardの真価は、一度システムを導入して終わりではない点にあります。特にSaaS型ERPを導入した場合、自社で大規模な開発投資を行うことなく、ベンダーが提供するAI、機械学習、IoTといった最新技術の恩恵を継続的に受けられます。 定期的なバージョンアップにより、システムは常に最新の状態に保たれ、新たなビジネス価値を創出し続けるのです。
この柔軟な経営プラットフォームは、企業の持続的な成長を力強く後押しします。例えば、新規事業の立ち上げやM&Aによる事業統合の際も、標準化された業務プロセスとシステム基盤があることで、迅速な展開が可能となります。 また、サプライチェーン全体のCO2排出量を可視化するなど、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営といった新たな要請にも柔軟に対応できる基盤が整います。Fit to standardは、単なるコスト削減や効率化に留まらず、未来のあらゆるビジネスチャンスを掴むための、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させる原動力となるのです。
まとめ
Fit to standardは、ERPの標準機能に業務を合わせることで、変化に強いシステム基盤の構築、TCOの最適化、ベストプラクティスの導入を実現する現代的な導入手法です。成功には、準備・実行・定着化の各フェーズを正しく理解し、進めることが不可欠です。特に、経営層の強いリーダーシップや業務部門の主体的な参画といった5つの成功ポイントを押さえることが成否を分けます。本記事を参考に、Fit to standardを成功させ、持続的な成長を支える経営基盤を築きましょう。
- キーワード:
- DX