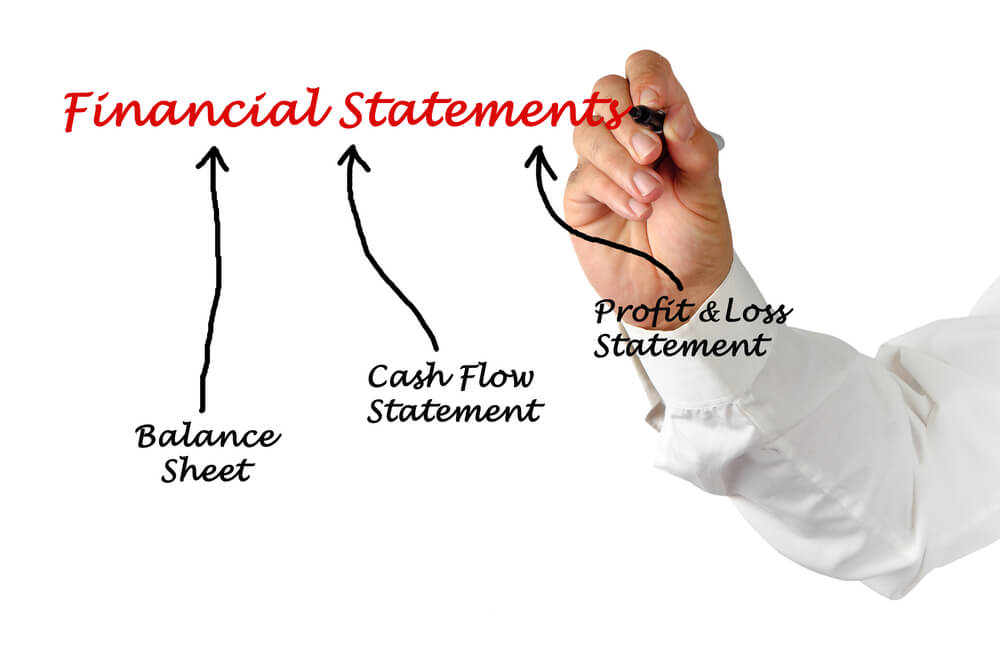IFRS(国際会計基準)は国際的に通用する企業会計の基準です。日本のみで通用する「日本会計基準」とは異なる点がいくつかあります。導入を検討する際には、IFRSと日本基準の違いを知ったうえで、どちらが適しているのかを判断することが大切です。本記事では、IFRSと日本基準それぞれの特長を紹介し、IFRSと日本基準の違いを解説します。また、IFRSのメリットとデメリットも解説します。これらを理解できると、自社にどちらが適しているのが見えてくるでしょう。
IFRS(国際会計基準)とは
IFRS(国際会計基準)は、International Financial Reporting Standardsの略称であり、国際会計基準審議会(IASB)が国際的に通用する企業会計の基準として策定したものです。欧州連合(EU)では、2005年からIFRSの取り入れをEU内の上場企業に義務づけてからIFRSを取り入れる国が急速に増えました。世界各国の会計制度はIFRSの影響を受けており、すでに130以上の国と地域で適用されています。IFRSは、グローバルスタンダードになりつつある会計基準です。
日本やアメリカなどでは義務化されていないため、日本では「日本会計基準」「米国会計基準」「国際会計基準(IFRS)」「修正国際基準(JMIS)」などの会計基準の中から自社に最適なものを選択できます。
IFRSは、「原則主義」「貸借対照表重視」「グローバル基準」の3つから成り立っている点が特長です。海外に数多くの子会社を有する企業や、海外の投資家から資金を集めたい企業が多く導入しています。

日本会計基準とは
日本会計基準は、日本国内で広く一般的に使われている会計基準です。1949年に制定された企業会計原則をベースに作られ、社会情勢の変化を受けて2001年に作り直しが行われました。日本特有の商慣習や会計慣行がベースになっているため、日本企業にとっては馴染みやすいのが特長です。日本企業の多くは日本基準を採用していますが、IFRSを採用する企業も増えました。
日本基準は、「一般原則」「損益計算書原則」「貸借対照表原則」の3つの原則から成り立っています。財務諸表の損益計算書は損益計算書原則、貸借対照表は貸借対照表原則に基づいて作ることになります。
IFRS(国際会計基準)と日本会計基準の違い
ここまで、IFRSと日本会計基準の内容について概説しましたが、両者には異なる点がいくつも存在します。導入を検討する際は両者の違いを知ったうえで、どちらの会計基準が自社に適しているのかを判断しましょう。ここでは、IFRSと日本基準の大まかな違いについて紹介します。
重要視する項目
IFRSと日本基準では重要視する項目が異なります。IFRSは貸借対照表を重要視するのに対して、日本基準は損益計算書を重要視します。貸借対照表は企業価値を表す財務諸表であり、損益計算書は企業の業績を表す財務諸表です。
税務への配慮
IFRSと日本基準は「税務への配慮」の点でも違いがあります。IFRSはあらゆる国での使用を前提とした企業会計の基準であり、各国の税務システムを考慮することはありません。税務システムは国によって異なるため、IFRSを導入する国ではIFRSを考慮した税務システムに変更する必要があります。
一方、日本は税務と会計が深く密接しており、税務は会計に強い影響を与えます。税務が会計に譲歩することはなく、会計に配慮して税務が変わることはありません。
のれんの償却
IFRSと日本基準の異なる点のひとつとして、のれんの償却が挙げられます。のれんとは、人的資源や企業が持っているネットワークなど「目に見えない価値」のことを指す言葉です。
IFRS(国際会計基準)では、規則的な償却は行わず、年1回の減損テストによって判断されます。規則的な償却が行われないため、IFRSを適用した場合、のれん償却費の分だけ利益が増加する可能性があります。
一方、日本基準では、のれんを計上してから20年間にわたり、定額法に則って規則的に償却する必要があります。そのため、のれん償却の期間中はのれん償却費の分だけ利益が減少することになります。
IFRSが日本企業の会計にもたらす影響
では、日本基準とさまざまな違いがあるIFRSの導入は、日本企業の会計にどのような影響をもたらすのでしょうか。
細則主義から原則主義へ
会計において、細則主義と原則主義という考え方があります。詳細な数値や基準、規定や指針などが定められているのが日本従来の細則主義です。
IFRSの特長である原則主義では、基本的な原則を定めるにとどまり、細かい数値や規定は定められていません。それゆえに自由度も高くなりますが、解釈の根拠を明示することが求められるので、膨大な注記が必要です。実務では、具体的な事例・状況ごとに判断する必要があります。
IFRSを導入し、細則主義とは正反対の原則主義が適用されれば、基準や規定は大きく変わるでしょう。
貸借対照表(B/S)重視
利益を求める考え方として、日本の会計基準は損益計算書を重視しますが、IFRSは貸借対照表(B/S)重視(資産負債アプローチ)をとっています。
資産負債アプローチとは、一会計期間において、貸借対照表における資産と負債の差額を利益として評価する考え方です。企業価値を明らかにするという目的があります。
日本の会計基準で採用されている収益費用アプローチは、一会計期間における収益と費用の差額を利益として算出する考え方であり、企業の安定性や継続性を測ることが可能です。
IFRSを導入すれば、貸借対照表がより重視されるようになり、厳密な解釈や理解が必要になるでしょう。
会計方針の統一
日本基準では、同一環境のもと行われた同一の取引・事象について、原則的に会計処理を統一する方針です。
IFRSでは、類似状況のもと行われた同様の取引・事象に統一の会計方針が適用されます。
そのため、IFRSの導入により統一された会計方針が採用されれば、マニュアルや体制の整備が必要です。
公正価値測定方法の新基準
2011年に国際会計基準審議会(IASB)は「公正価値測定」を公表し、IFRSの公正価値測定方法が新基準に統一されました。
公正価値とは日本における「時価」とほぼ同じ意味であり、IFRSでは「資産を売却するために受け取る見込みの価格」あるいは「負債を移転するために支払う見込みの価格」です。
IFRSの新基準では、公正価値についての指針が示されており、それに基づいた「インプット」と「評価技法」によって公正価値を測定・開示します。
IFRSが生まれた背景
IFRSは、どのような社会情勢や背景のもとで生まれたのでしょうか。IFRSの沿革について解説します。
グローバル化が進み国境を越えた会計基準が求められるように
従来は、貿易など国境を越えたビジネスであっても、国や地域ごとに異なった会計基準を運用するのが常識でした。しかし、経済活動のグローバル化に伴い、一定の会計基準で統一する必要性が高まっています。
例えば、投資家は財務諸表などの情報をもとにして会社の価値を判断します。しかし、国ごとに別々の会計基準で財務諸表が作成されると、比較可能性の確保が難しくなります。このような弊害を受け、国境を越えて適用可能な会計基準のニーズが高まったことでIFRSが策定されました。
IFRSの歴史は1970年代にまで遡る
IFRSそのものが誕生したのは2000年以降ですが、その歴史は1970年代まで遡ります。
国際会計基準審議会(IASB)の前身である国際会計基準委員会(IASC、International Accounting Standards Committee)が1973年に発足しました。IASCは財務諸表の比較可能性を高めることを目的として、1978年から国際会計基準(IAS、International Accounting Standards)の作成に着手しています。
IASCは日本やオーストラリア、アメリカやイギリスなど9か国の会計士団体により設立されましたが、当時の影響力は決して強くありませんでした。
1986年に発足した証券監督者国際機構(IOSCO、International Organization of Securities Commissions)は多国間公募の拡大を受けてIASCに関心を持ち、1988年のメルボルン総会でIASCへの活動支持を表明します。国際的機関であるIOSCOからの支持を受けて、IASCの活動は活発化し、その影響力は次第に大きくなっていきます。
1989年から始まったIASの改訂作業は1993年に完了しました。
2001年にIASCは改組され、IASC財団(IASC Foundation)の一部として国際会計基準審議会(IASB、International Accounting Standards Board)が発足し、より強固な組織になりました。このとき、IASの名称はIFRSに改められ、以降はIFRSの改訂が進められています。
2010年にIASC財団はIFRS財団へ改称され、現在に至ります。IFRS財団は民間の非営利組織であり、目的は国際的に認められた財務報告基準の開発です。
2002年の「ノーウォーク合意」では、米国財務会計基準審議会(FASB)はIASBへの協調姿勢を示しています。2005年12月期以降、EU域内の上場企業の連結財務諸表にIFRSが強制適用され、2008年のG20では「単一で高品質な国際基準を策定する」ことが目標として掲げられました。
このような状況・情勢の変化の中でIFRSは急速に普及し、世界的な会計基準として認識されるようになっていきます。
日本企業のIFRSへの対応状況
これまで、また現在において、日本企業はどのようにIFRSに対応しているのでしょうか。
これまでの日本の対応
IFRSは、国によって強制適用や任意適用、コンバージェンスなど異なる方法で取り入れられています。
コンバージェンスとは、アメリカや日本が実施しており、自国の会計基準を保持しつつ、IFRSに歩み寄るものです。
2007年、日本の企業会計基準委員会(ASBJ、Accounting Standards Board of Japan)とIASBは東京合意において、2011年までに日本の会計基準をIFRSにコンバージェンスさせることを決めました。2005年のEU域内のIFRS強制適用を受けて日本でもIFRSを取り入れる動きが生じていましたが、東京合意以降、日本はコンバージェンスの方針へ加速します。
2009年に金融庁は「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」を発表しました。これは日本のIFRS導入に向け、2010年3月から国際的な活動を行う上場企業の連結財務諸表にIFRSを任意適用することを認め、強制適用は2012年を目途に判断するというものです。
コンバージェンスの扱いについても検討会議が設置され、審議が重ねられています。2011年6月時点で、金融大臣は「2015年の強制適用は検討しておらず、強制適用の場合は5~7年の準備期間を設定する」と述べています。
2011年の東日本大震災による影響や米国の対応遅延を受け、IFRSの強制適用は見送られました。2012年に公表された「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」では、IFRSの適用において、日本経済や従来の制度への影響を考慮したうえで最適な対応をすべきという内容が示されています。
それ以降も強制適用はなされず、2016年に修正国際基準(JMIS、Japan's Modified International Standards)が適用可能になりました。これは、IFRSの一部を日本向けにしたもので、変更点はのれんの定期償却ができる点と、株式売買損益を純利益に反映できる点です。
2021年4月以降、IFRSを取り入れた「収益認識に関する会計基準」が一部の企業に強制適用されます。対象となる企業は、監査を受ける上場企業や大企業です。
日本ではこのような変遷を経て、IFRSに適応しつつあります。
参考元:
「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」の公表について(金融庁)
「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」の公表について(金融庁)
現在のIFRS適用企業数は250社を超える
2010年にIFRSが任意適用されて以来、IFRSを取り入れる企業は増加し続けました。IFRSに対応するため、さまざまな組織やチームが発足し、取り組みが行われています。
日本取引所グループの調査によると、2022年8月時点で日本におけるIFRS適用企業数は250社を超えています。上場企業や大企業だけでなく、多数の中小企業も適用済みです。サービス業や情報・通信業、電気機器や小売業などの幅広い業種が適用している一方で、銀行や海運業、保険会社や建設業などで適用を受けている企業はありません。特に金融機関では、適用により業務に大きな影響が及ぶため、入念なシステム構築や準備が必要でしょう。
東証上場企業3,770社のうち、IFRSをまだ適用していない会社(検討企業を除く)は3,351社であり、適用している会社の数は全体の10%にも及びません。しかし、IFRS適用済会社とIFRS適用決定会社、IFRS適用予定会社を合わせた時価総額は316兆円となり、東証上場会社全体のうち時価総額の45.1%に及びます(2022年6月時点)。IFRSの適用を検討する会社を含めると、割合はさらに大きくなります。
参照元:
IFRS(国際財務報告基準)への対応(JPX)
「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容の分析について≪2022年3月期決算会社まで≫(JPX)
IFRSを導入するメリット・デメリット
IFRSを導入することで、企業には多くのメリットがあります。一方、導入により生じるさまざまな課題・問題が懸念されます。デメリットがなぜ生じてしまうのか、原因をしっかり押さえましょう。
メリット1. 資金調達の方法が増える
IFRSは国際的に通用する企業会計の基準です。そのため、外国人投資家から資金を調達しやすくなります。IFRSに基づいて財務諸表を作り上げることで、外国人投資家に自社の企業価値をアピールすることが可能です。
また、外国人投資家に対して日本基準とIFRSの違いを説明する必要もありません。外国人投資家はIFRSに基づいて作り上げられた財務諸表を確認することで、投資対象として適切であるかどうかを判断できます。
外国から投資を呼び込みたい企業は、導入を検討するとよいでしょう。
メリット2. 国外の子会社・部門の管理がしやすくなる
国外に子会社や拠点を構えている日本企業はIFRSを取り入れることで、国外の子会社・部門の管理がしやすくなります。特に、IFRSを取り入れている国に子会社や拠点を構えている日本企業にとっては、大きなメリットになるでしょう。
日本の本社と国外の子会社・部門が共通の会計基準で財務諸表を作ることで、数字の比較を正確に行えるようになります。精度の高い経営分析が可能になるでしょう。
また、IFRSに基づいて作り上げた財務諸表を海外でもそのまま流用することもできます。わざわざ海外用に財務諸表を新たに作り替える必要はないため、無駄な手間が省けるでしょう。
メリット3. 業績を適切に反映させやすくなる
IFRSを取り入れることで、業績を適切に反映させやすくなります。
IFRSでは規則的なのれん代の償却はなくなるため、利益が増えます。しかし償却がない分、発生する減損は日本基準よりも大きくなるでしょう。減損損失を計上すれば、より正確な資産価値が財務諸表に反映されます。
IFRSでは、一定期間の利益を「継続事業からの当期利益」「非継続事業からの当期利益」に分けます。非継続事業とは、期末までに廃止、または売却された事業です。非継続事業から生じる損益は、企業の将来予測にあまり関わりません。
この区分により業績が正確に反映されるため、将来のキャッシュフロー予測が立てやすくなります。
貸借対照表を重視するIFRSの基準で財務諸表を作成すれば、日本基準よりも業績を正確に把握できるようになるでしょう。
デメリット1. 事務負担が増加する
IFRSを取り入れるデメリットとして、事務負担が増加する点が挙げられます。日本企業がIFRSを取り入れた場合、IFRSに基づいて連結計算書類を作り上げても、個別財務諸表は日本基準に基づいて作り上げる必要があります。
また、IFRSを取り入れた場合には、英語で財務諸表を作らなければなりません。そのためには、高度な英語力を有する人材が必要です。加えて、国際会計の専門知識も不可欠でしょう。両方の条件を満たす優秀な人材の確保は難しいかもしれません。人材を育成する知識を持った社員も必要であり、マニュアルなどの整備も必要になります。
デメリット2. 導入に費用と時間がかかる
導入に費用と時間がかかる点もデメリットです。IFRSに基づいて財務諸表を作り上げなければなりません。人材育成には費用と時間、労力がかかるでしょう。
また、IFRSに対応した会計システムの構築や既存の会計システムの変更も必要になってくるため、そのための費用や時間を捻出する必要もあります。このように、IFRSを取り入れるためのハードルは複数あります。
IFRSを導入すべき企業
海外と取引があり、資金や人材が豊富な企業の多くはIFRSを取り入れています。
IFRSを導入すべきかについては、海外売上比率、時価総額、営業利益の3点から判断します。海外売上比率と時価総額が高く、IFRS導入のコスト以上の営業利益がある企業は、IFRSを導入すべきでしょう。
現在・将来において、活動範囲を日本に限定する企業にとっては、IFRSを導入するメリットはあまり多くありません。将来的に海外進出を予定するならば、進出する国によってはIFRSの導入が必須の場合もあるため、早期から検討するとよいでしょう。
IFRSを導入する際のポイント
IFRSを導入する際には、以下のポイントを押さえましょう。
- 事前の綿密な計画
IFRSは日本従来の会計基準とは多くの相違点があるため、導入すれば経営に大きな影響を及ぼします。そのため、事前の綿密かつ慎重な検討が必要です。
まずは計画書を作成し、方針を固め、財務諸表の雛型を作成します。導入に向けて担当部署・担当者を配置し、専門家の雇用を検討するのもよいでしょう。
IFRSを取り巻く情勢は常に変化するため、最新の知識・情報を更新し続けることも求められます。導入時だけでなく、導入後の具体的な計画も練る必要があります。 - 社員への教育
会計処理に携わる社員に加え、関連部署の社員への教育が必要です。IFRSについて全社員が理解するために、セミナーの開催などで認知や教育の機会を作りましょう。教育プログラムやマニュアルを作成し、全体の知識を深めるとともに、変更する業務内容やルールを周知・徹底させます。 - システムの変更
会計システムや業務フローの構築・変更には、膨大な時間と労力がかかります。
アプリケーションなどを活用すれば手間を大幅に省くことができ、ミスも減らせるでしょう。
IFRSの導入は、会計処理だけでなく会社経営に大きな影響を与えます。基本的にIFRS適用は数年がかりのプロジェクトになることを前提として、あらゆる状況を想定しましょう。
[RELATED_POSTS]まとめ
IFRSはグローバルスタンダードになりつつある国際的な会計基準です。重要視する項目をはじめ日本会計基準とは多くの違いがあり、導入すれば企業会計においてさまざまな変更・方針転換が必要になるでしょう。
現在、多くの日本企業がIFRSを適用しています。IFRSを取り入れれば、外国人投資家からの資金の調達がしやすくなり、国外に子会社や拠点を構える日本企業は管理がしやすくなります。
このようなメリットがある一方で、事務負担やコストなどの問題もあります。導入によるメリットとコストを比較し、どちらがより重要なのかを考えましょう。
IFRSの適用には膨大な準備やシステム構築が必要になるため、クラウドERPの導入がおすすめです。NetSuite ERPは19種類の言語に対応しているため、海外に支社や子会社を持つ企業でもスムーズに導入できます。オラクル社によるERPパッケージであるOracle E-Business Suiteは、世界中の企業で利用されており、複数言語・会計基準に対応しています。
この機会にぜひ検討してみてください。
- カテゴリ:
- 会計
- キーワード:
- 経理/財務会計