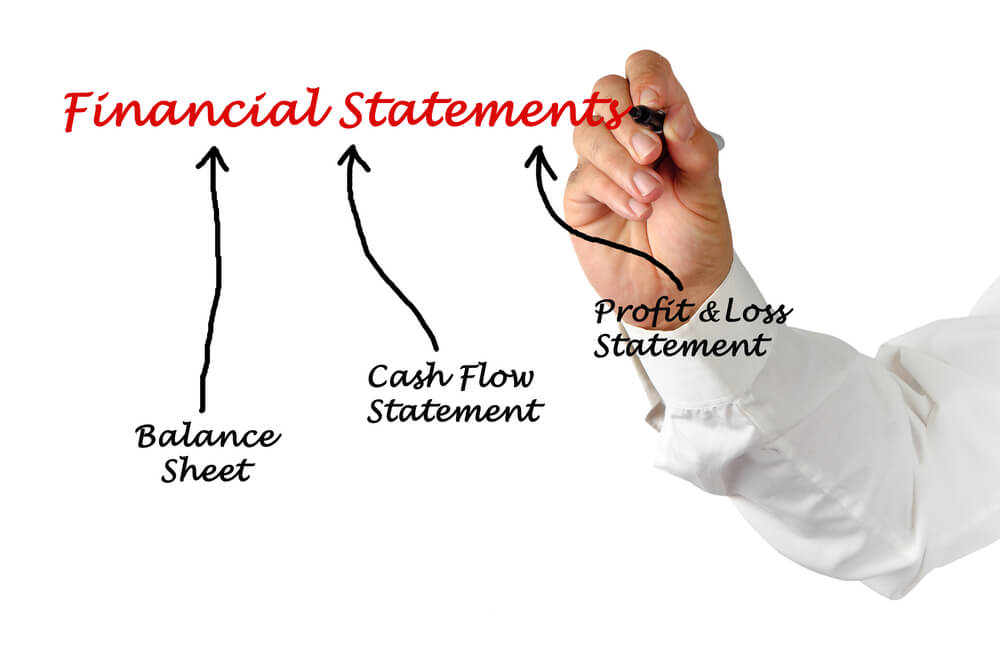決算の早期化(決算早期化)の需要は依然として高いままです。現在では「タイムリーな経営分析・意思決定」を促すことを目的として取り組む企業が多いでしょう。しかし、決算早期化を実現するにあたり、さまざまなボトルネックに悩んでいる企業は珍しくありません。ほとんどの企業では年度末にはかなりの労力を使っていることでしょう。本記事では、決算早期化を実現する上で欠かせないコツやポイントについてご紹介します。
決算早期化の目的・メリットとは?
決算早期化は、その名の通り決算を早期に実施することです。決算早期化するためには、まず月次決算の目的やメリットを把握しておかなければなりません。納税額の決定や財政状況の総括をする年次決算とは違い、月次決算は経営状態の現状を把握して今後の経営判断を行うために実施します。必ず行うべきものではありませんが、月次決算を行うことで、年次決算および中間決算の準備負担を軽減できることや、金融機関等への資料提出もスムーズになります。
この中でも、特に大きなメリットは年次決算の負担軽減ではないでしょうか。東京証券取引所が2020年6月に発表した「2022年3月期決算発表状況の集計結果について」によると、2022年3月期決算発表会社数は2,288社(前年2,302社)であり、決算発表までに要した日数は40.3日(前年40.8日)となっています。前年度より、0.5日短縮したとはいえ、同取引所の「決算短信・四半期決算短信 作成要領等」によると、決算期末後30日以内の開示が「より望ましい」とされています。このことから、決算早期化に対する意識は高めていく必要があります。
決算早期化を実施することで、以下のメリットが得られます。
- 経営戦略の立案や意思決定の迅速化
- 正確な売上・利益予測
- 決算業務の短期化による他業務の効率化
- 経理担当者の残業時間削減
- 投資家への速やかな情報提供
決算早期化を実施することのメリットはいずれも経営上重要なものであり、これらのメリットを最大限引き出せれば、経営最適化や資金繰り改善なども行えます。
出典:2022年3月期決算発表状況の集計結果について
出典:決算短信・四半期決算短信 作成要領等
決算早期化が遅れる理由
決算早期化を実施することでさまざまなメリットが得られますが、依然として進んでいないのが現状です。決算早期化の実施が遅れている理由としては、以下の事項が考えられます。
- 月末月初に作業が集中し、負担が大きい
- 決算業務を担当する人員が不足している
- 勘定科目の金額を確定するのに時間を費やしてしまう
- 手入力における作業時間が長期化する
上記以外にも、企業の規模または決算業務で行う内容の範囲などは決算早期化が遅れる理由になり得ます。
たとえば、グループ会社を保有していることから連結決算が必要な場合です。決算対象がグループ全体に及ぶため、財務数値の把握に時間を要してしまいます。加えて、リコンサイル(帳簿間の勘定照合)を行うことで、さらに決算が遅れやすくなります。
決算早期化を実施する際のチェックポイント
決算早期化を実現するための具体策としてまず思い浮かぶのが「決算業務の前倒し」でしょう。決算期末日前に決算業務を前倒しすることによって、決算早期化を図り、経理担当者の業務効率化に繋げられます。そのためのチェックポイントとは何でしょうか?
1.総工数の削減ではなく、決算ピーク時の業務軽減を優先しているか?
決算日前に決算業務を前倒しする場合、注意したいポイントは前倒しによって決算期末日後の業務が減少するものもあれば、中には決算期末日後に再度更新しなければいけない業務もあります。たとえば期中取引の会計処理確認は前者、親会社と同じ決算日の子会社株式評価は後者にあたります。
決算早期化では全体の総工数削減を目指すケースが多いですが、それでは決算期末日後も同じように負担が発生する場合があります。そのため、決算ピーク時に業務負担が軽減されることを優先し、決算期末日後の業務が減少するような業務前倒しを実施することがとても重要になります。
2.担当者レベルではなく組織レベルで検討しているか?
決算業務の前倒しを担当者レベルではなく、組織レベルで検討するということも大切なポイントです。これまで決算早期化に取り組んでこなかった企業では、業務の前倒しを実施することにより、決算ピーク時における経理担当者の業務負担が大幅に減少されます。
しかしながら、経理担当者によって減少される業務負担に差が出やすいこともあり、担当者レベルではなく組織レベルで業務前倒しを検討し、経理担当者ごとに業務負担を平準化することが肝要です。従って、時には業務分担の抜本的見直しが必要になります。
3.決算業務は決算日前から開始しているという意識は持てているか?
決算日を過ぎてから「決算業務の開始だ!」と気持ちを切り替える企業は多いでしょう。しかし、決算早期化を実現したいのであれば「決算業務は決算日前から始まっている!」という意識改革を行う必要があります。こうした意識改革は経理責任者が中心になって経理部門全体に浸透させることが、決算早期化を実現する上でとても大切なポイントです。
決算業務の前倒しを実施する際は、以上3つのチェックポイントに意識しながら進めていくことで、ボトルネックを解消しつつ決算早期化に取り組めます。
決算資料作成におけるチェックポイント
決算早期化にあたり、必ず押さえておいていただきたいポイントが「決算資料作成」です。決算業務の中ではトップレベルの業務負担なので、如何に効率良く正確な決算資料を作成できるかが決算早期化のコツになります。決算資料作成にあたっては、以下のチェックポイントに注意してみましょう。
1.経理責任者のチェックを意識した決算資料作成はできているか?
決算資料作成における基本ポイントは「とにかく分かりやすい内容で作成する」です。決算資料のチェックを徹底することで、手戻りを少なくできますが、その分チェックに時間がかかってしまうというケースは少なくありません。その際に、経理責任者のチェックを意識して分かりやすい決算資料作成を心掛けることで、かなりの工数を削減できます。
たとえば勘定明細や開示書類の元資料において、支店や関係会社の記載順番がバラバラになっているケースは多いでしょう。これを五十音順に並べ替えるだけでもチェック時間は短縮できます。決算資料作成にあたって基本的なルールを作り、各経理担当者がそれを徹底することが大切です。
2.類似した情報、同時に検討すべき論点は1ヵ所に集約しているか?
似たような資料はまとめて作成し、相互関連し同時に検討すべき事項については併せて検討することが決算早期化のコツです。類似した情報や同時に検討すべき論点が分散していると、チェックが複雑になるばかりではなく、途中で修正が発生した場合の資料更新に遅れや漏れが発生してしまいます。決算早期化の実現だけではなく、正確な決算資料を作成するためにも欠かせないチェックポイントです。
3.見積項目に関する十分な説明はされているか?
繰延税金資産の回収可能性の検討のような見積項目については、経営者が想定した過程や判断にもとづく項目であるため、客観的合理性を持って説明できるかどうかがポイントになります。見積項目に関しては監査人の関心も高いため、監査対応の工数削減を実施するためにも、第三者を十分に納得させられる説明を適切に文書化することが大切です。
決算早期化を実現した事例紹介
多くのメリットが得られる決算早期化は、近年さまざまな企業が積極的に取り組んでいます。ここでは、会計・財務、販売管理などを一元化できる基幹業務システム、ERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)を導入し、決算早期化を実現している企業2社を紹介します。
Oracle(オラクル)
グローバル企業であるOracleでは、2013年より自社サービスである「Oracle ERP Cloud」を導入することで、決算早期化を実現しています。
コロナ禍以前からリモート業務を取り入れ、なおかつ伝票などもペーパーレスにしていることで、業務効率化および決算業務も迅速に行うことを可能にしました。また、2018年からは決算業務においてもクラウド化し、連結決算でありながらも、決算早期化を実現しています。
Oracleでは今後も自動化を推進し、決算業務においては決算を1日で締める「ワンデイクローズ」を目指しています。「Oracle Cloud EPM」の機能を活用することで業務を標準化し、多くの子会社からの数字を集約しなければならない連結決算のさらなる効率化にも取り組みます。
また、自動化についても「Oracle ERP Cloud」の機械学習機能やAI機能を拡張していくことで、経理業務における自動化の比率を高めていきます。
Panasonic(パナソニック)
家電から住宅まであらゆる分野で革新的な技術を展開するグローバル企業のPanasonicは、多様なアプリケーション製品の中から「Oracle Cloud ERP」および「Oracle Cloud EPM」を採用しました。
採用に至った理由は、ひとつの取引に財務・非財務カテゴリ情報を保有できることや分析レポート機能の実装、さらには組織再編などの変更に対しても対応可能な柔軟性・拡張性を有することなどです。
これらの採用により、決算業務における大幅な工数削減だけでなく、戦略的経営判断に貢献する連結管理会計による多軸分析を実現しました。
[SMART_CONTENT]クラウドアプリケーションの導入によって決算早期化を実現
あらゆる業務においてDXが進む中、財務業務においては自動化が遅れているのが現状です。その中で、クラウドアプリケーションを導入することにより、単体決算だけでなく連結決算における決算早期化を実現できます。
Oracleのクラウドアプリケーション「Oracle EPM Cloud」では、連結決算業務の自動化および予算管理、経営管理の高度化が可能です。連結決算業務では、連結決算・リコンサイル(勘定照合)・決算開示・報告書作成までの自動化を実現します。特に、Excelなどで行う手入力ではミスが頻発するため時間がかかり管理も困難なリコンサイル業務においてはOracle EPM Cloud導入の恩恵が大きく、結果として担当者の負荷を軽減できます。
連結決算では業務内容だけでなく、子会社それぞれの担当者が多岐に渡ることから、誰がどの作業をいつまでに行う必要があるのかを明確にしなければなりません。Oracle EPM Cloudの導入により、決算業務の可視化を実施し、なおかつ自動化することで決算早期化を実現できます。
[RELATED_POSTS]
決算早期化を目指そう!
以上のように、さまざまなチェックポイントを押さえることで決算早期化を実現できます。また、クラウドERP であるNetSuiteなどを活用することでグローバルレベルでの決算の早期化を実現することも可能になります。
決算早期化によって様々なメリットを引き出し、経営最適化を図っていきましょう。
- カテゴリ:
- 会計
- キーワード:
- 経理/財務会計