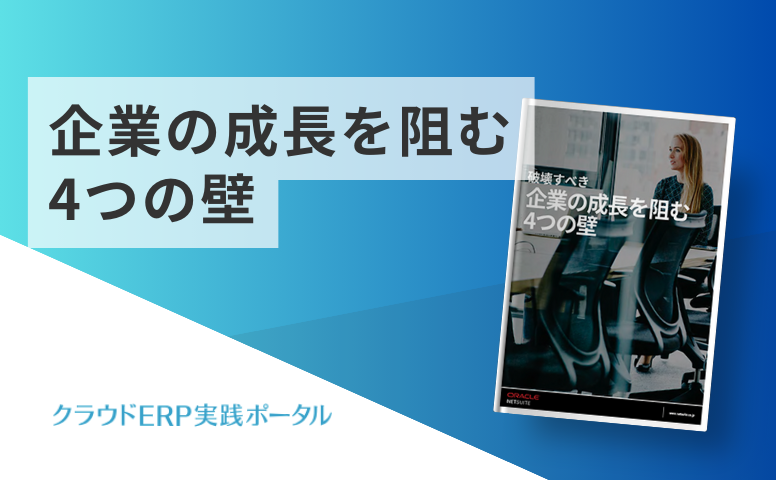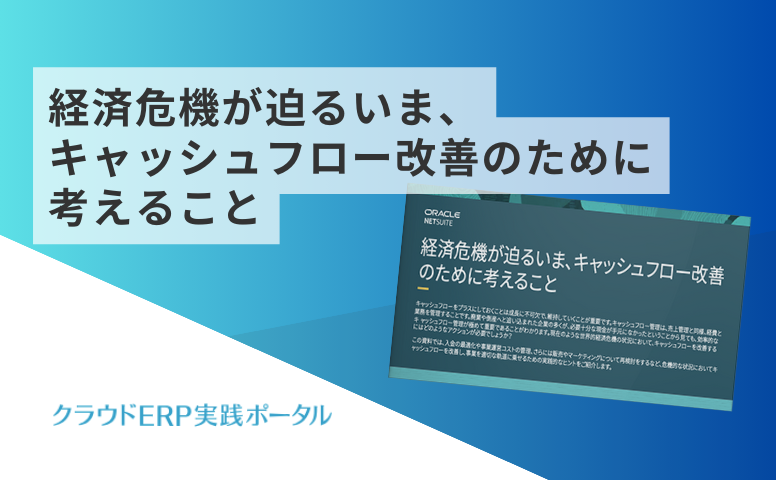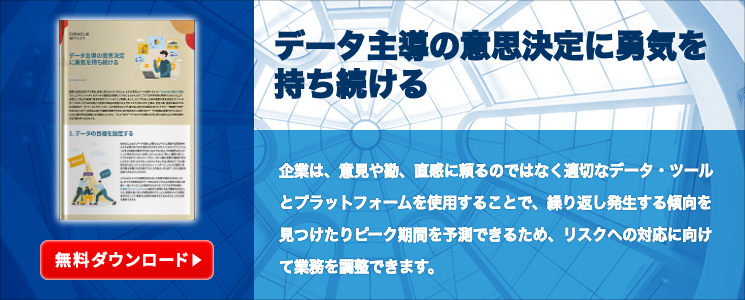経営管理とは、企業の目標達成という航海を導く重要な羅針盤です。しかし、その役割や経営企画との違い、具体的な仕事内容を正しく理解している人は少ないかもしれません。本記事を読めば、経営管理の目的から具体的な業務、必要なスキルまで、初心者の方でも体系的に理解できます。企業の成長を支える経営管理の全体像を、わかりやすく解説します。
経営管理とは 企業の成長を支える羅針盤
企業の持続的な成長と発展を目指す上で、その舵取り役を担うのが「経営管理」です。変化の激しい現代のビジネス環境において、企業という船が目的地に向かって正しく航海するためには、信頼できる羅針盤が不可欠です。経営管理は、まさにその羅針盤として機能し、組織全体の進むべき道を示し、目標達成へと導きます。
この章では、まず経営管理の基本的な意味合いと、なぜ今、多くの企業でその重要性が叫ばれているのかについて、基礎から丁寧に解説していきます。
経営管理の基本的な定義
経営管理とは、企業が掲げたビジョンや目標を達成するために、ヒト・モノ・カネ・情報といった「経営資源」を最も効率的かつ効果的に活用するための仕組みや活動の総称です。単に数値を管理するだけでなく、組織全体のパフォーマンスを最大化させるための計画立案、実行、進捗確認、そして改善までを含む一連のプロセスを指します。
経営学の父と称されるピーター・ドラッカーは、企業の目的を「顧客の創造」とし、その目的を達成するためのマネジメントの重要性を説きました。経営管理は、このマネジメントの中核をなす概念であり、企業のあらゆる活動の土台となります。
具体的には、経営管理は以下のようなサイクルで機能します。これは「マネジメント・サイクル」とも呼ばれ、多くの企業活動の基本となっています。
| プロセス | 主な活動内容 |
| 計画(Plan) | 企業の目標を設定し、その目標を達成するための具体的な戦略や行動計画、予算などを策定します。 |
| 組織化(Organize) | 計画を実行するために、必要な人材や部署を配置し、権限や責任を明確にして、効率的に業務が進む組織構造を構築します。 |
| 指揮(Lead / Direct) | 従業員のモチベーションを高め、リーダーシップを発揮しながら、組織全体が計画通りに行動するよう導きます。 |
| 統制(Control) | 計画と実績を比較・評価し、目標達成に向けた進捗を管理します。問題点や課題が見つかれば、それを修正するためのアクションを起こします。 |
このように、経営管理は一度計画を立てて終わりではなく、常に状況を把握し、軌道修正を繰り返しながら企業をゴールへと導く、動的な活動なのです。
なぜ今経営管理が重要視されているのか
近年、テクノロジーの進化やグローバル化の進展により、ビジネスを取り巻く環境はかつてないほど複雑化し、変化のスピードを増しています。このような時代背景から、経営管理の重要性はますます高まっています。その主な理由は、次の3つです。
VUCA時代における的確な意思決定の必要性
現代は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った「VUCA(ブーカ)の時代」と呼ばれています。市場のニーズ、競合の動向、技術革新など、あらゆるものが目まぐるしく変化し、将来の予測が非常に困難な状況です。このような環境下では、過去の成功体験や経営者の勘だけに頼った経営判断は、大きなリスクを伴います。客観的なデータに基づき、現状を正確に分析し、未来を予測する経営管理の仕組みがなければ、変化の波に乗り遅れ、企業の存続すら危うくなる可能性があります。
企業間競争の激化と資源の有限性
グローバル化により、競争相手は国内企業に留まらず、世界中の企業がライバルとなります。また、多くの市場で製品やサービスが成熟し、他社との差別化が難しくなっています(コモディティ化)。このような厳しい競争環境で勝ち抜くためには、自社が持つ限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)をいかに効率的に配分し、最大限の成果を生み出すかが極めて重要です。経営管理は、資源の無駄をなくし、投資対効果を最大化するための羅針盤として機能します。
働き方の多様化と組織マネジメントの高度化
終身雇用制度が過去のものとなり、人材の流動性が高まる中、企業は多様な価値観を持つ従業員をまとめ、組織としての一体感を醸成する必要に迫られています。また、リモートワークの普及は、従来の対面を前提としたマネジメント手法の見直しを求めます。明確な目標(KPI)の設定、公正な業績評価、そして円滑なコミュニケーションを支える経営管理の体制を構築しなければ、従業員のエンゲージメントを高め、組織全体の生産性を向上させることは困難です。優れた経営管理は、優秀な人材を惹きつけ、定着させる上でも不可欠な要素となっています。
経営管理と関連用語の違い
経営管理という言葉は、ビジネスの現場で「経営企画」や「財務管理」「管理会計」といった用語としばしば混同されがちです。しかし、それぞれには明確な役割と焦点の違いがあります。企業の成長を効果的に推進するためには、これらの用語の違いを正しく理解し、各機能がどのように連携するのかを把握することが不可欠です。ここでは、経営管理と混同されやすい主要な用語との違いを、具体的な業務内容や目的の観点から詳しく解説します。
経営企画との違い
経営企画と経営管理は、どちらも企業の舵取りを担う重要な機能ですが、その役割と時間軸に大きな違いがあります。端的に言えば、経営企画が「企業の未来の地図を描く」役割であるのに対し、経営管理は「その地図を基に航海が計画通りに進んでいるかを確認し、軌道修正する」役割を担います。
経営企画は、市場環境や競合の動向を分析し、「企業としてどこへ向かうべきか(Where)」、「何をすべきか(What)」という中長期的な視点での戦略を立案します。これには、新たな事業領域への進出やM&A(合併・買収)の検討、事業ポートフォリオの最適化などが含まれます。つまり、未来志向で変革を主導する「攻め」の機能と言えるでしょう。
一方、経営管理は、経営企画が策定した戦略や計画が着実に実行されるように、組織全体を動機づけ、統制する活動です。策定された計画を具体的な数値目標(予算)に落とし込み、日々の業務活動が目標達成に貢献しているかをモニタリング(予実管理)します。そして、計画と実績に乖離が生じた場合は、その原因を分析し、改善策を講じることで、目標達成の確度を高めます。こちらは、計画の実行を確実にする「守り」や「統制」の側面が強い機能です。
以下の表で、両者の違いを整理します。
| 項目 | 経営企画 | 経営管理 |
| 主な役割 | 企業の進むべき方向性を定め、中長期的な戦略を立案する(未来を構想する) | 策定された戦略に基づき、目標達成のための活動を統制・支援する(現在を管理する) |
| 時間軸 | 中長期(3年〜10年程度) | 短期〜中期(月次、四半期、年次) |
| 焦点 | What(何をすべきか) Where(どこへ向かうか) |
How(どう達成するか) Are we on track?(計画通りか) |
| 主な業務内容 | 経営理念・ビジョンの策定、市場・競合分析、新規事業計画、M&A戦略の立案、中期経営計画の策定 | 予算編成、業績評価(KPI設定・モニタリング)、予実管理と差異分析、業務プロセスの改善、部門間の調整 |
| 機能の性質 | 変革を促す「攻め」の機能 | 計画実行を確実にする「守り・統制」の機能 |
財務管理や管理会計との違い
財務管理と管理会計は、経営管理を実践するための重要な構成要素であり、ツールや手法と位置づけられます。経営管理という大きな枠組みの中で、これらが専門的な情報を提供し、意思決定を支える関係性にあります。財務管理や管理会計が「羅針盤や海図といった航海計器」だとすれば、経営管理は「それらの計器を読み解き、船全体を指揮する船長」の役割に例えられます。
財務管理(Financial Management)は、企業の活動に不可欠な「資金」に焦点を当てた管理活動です。主な目的は、企業の支払い能力を維持し、倒産リスクを回避すること、そして企業価値を最大化するための最適な資金調達と運用を行うことです。銀行からの借入や株式発行による資金調達、設備投資の判断、手元資金(キャッシュフロー)の管理など、主にお金の流れを外部(投資家、金融機関など)の視点も意識しながら管理します。
管理会計(Managerial Accounting)は、法律で定められた財務会計とは異なり、経営者や社内の管理者が意思決定を行うために活用する社内向けの会計手法です。目的は、経営判断に役立つ情報を提供することにあります。例えば、製品別の原価計算、部門別の採算性分析、事業の将来性を測るためのシミュレーション、予算と実績の比較分析などが含まれます。社内ルールに基づき、目的に応じて柔軟に設計できるのが特徴です。
経営管理は、これら財務管理や管理会計から得られる情報を統合的に利用します。管理会計が示す「どの事業が儲かっているか」という情報と、財務管理が示す「会社全体で資金は足りているか」という情報を組み合わせ、「利益が出ている成長事業に、限りある資金を重点的に配分する」といった全社最適の意思決定を下すのが経営管理の役割です。つまり、財務管理や管理会計は経営管理のための情報提供機能であり、経営管理はそれらを用いてPDCAサイクルを回し、企業全体のパフォーマンスを向上させる活動そのものを指します。
| 項目 | 経営管理 | 財務管理 | 管理会計 |
| 目的 | 企業目標の達成、意思決定支援、経営資源の最適配分 | 資金の最適化(調達・運用)、財務的安定性の確保、企業価値の向上 | 経営層や管理者の社内における意思決定に役立つ情報提供 |
| 情報の利用者 | 経営層、各部門の管理者 | 経営層、財務担当者、投資家、金融機関など(社外も含む) | 経営層、各部門の管理者など(社内限定) |
| 準拠するルール | 独自の経営方針や戦略 | 会社法や金融商品取引法、会計基準なども意識する | 社内独自のルール( gesetzliche Vorschriften なし) |
| 主なアウトプット | 経営戦略、予算実績管理レポート、KPIダッシュボード、改善提案書 | 資金繰り表、キャッシュフロー計算書、投資計画書、財務戦略 | 部門別・製品別損益計算書、原価計算書、予実対比表、事業採算性分析レポート |
| 位置づけ | 各管理活動を統合し、企業全体のパフォーマンスを最大化する活動 | 経営管理を支える「資金」に特化したサブシステム | 経営管理を支える「情報提供」に特化したサブシステム |
経営管理の3つの主要な目的

経営管理は、単に企業の現状を把握するだけの活動ではありません。企業の未来を創造し、持続的な成長を達成するための能動的な舵取りそのものです。ここでは、その羅針盤とも言える経営管理が果たすべき、3つの主要な目的について詳しく解説します。
企業のビジョンと目標の達成
企業が掲げる壮大な「ビジョン(理想像)」や「ミッション(使命)」は、それだけでは絵に描いた餅に過ぎません。経営管理は、この抽象的なビジョンを具体的な「目標」に落とし込み、組織全体で達成へと向かうための道筋を描く重要な役割を担います。全社的な方向性を統一し、従業員一人ひとりの日々の業務を同じゴールへと結びつけること、それが経営管理の第一の目的です。
具体的には、長期的なビジョンから中期経営計画、そして各部署や個人の年度目標へとブレイクダウンしていきます。このプロセスを通じて、経営層から現場の従業員までが「自分たちの仕事が会社の未来にどう貢献するのか」を明確に理解できるようになります。これにより、組織の一体感が醸成され、目標達成に向けた強力な推進力が生まれるのです。
| 階層 | 内容 | 具体例 |
| ビジョン | 企業の究極的な理想像・ありたい姿 | 「10年後に、革新的なテクノロジーで人々の暮らしを支えるリーディングカンパニーになる」 |
| 経営戦略 | ビジョン達成のための中長期的な方針 | 「高付加価値製品群の開発と、アジア市場への本格展開」 |
| 目標(KGI) | 戦略の達成度を測る具体的な指標 | 「3年後の売上高1,000億円達成、海外売上比率を30%に向上」 |
| 戦術・施策 | 目標達成のための具体的な行動計画 | 「研究開発予算を20%増額」「現地販売代理店とのパートナーシップ強化」 |
迅速で的確な意思決定の支援
現代のビジネス環境は、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)時代とも言われ、変化のスピードが非常に速く、将来の予測が困難です。このような状況下で経営者が下す一つひとつの判断が、企業の将来を大きく左右します。経営管理の第二の目的は、経営者の勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータや事実に基づいて、迅速かつ的確な意思決定を行えるよう支援することです。
経営管理は、月次決算や業績予測、各種分析レポートといった「管理会計情報」をタイムリーに提供します。これにより、経営層は以下のような重要な経営判断を、より高い精度で行うことが可能になります。
- 事業投資の判断:新製品を市場に投入すべきか、どの事業に注力すべきか。
- 撤退の判断:不採算事業から撤退し、経営資源を再配分すべきか。
- 価格戦略の判断:競合の動向やコスト構造を踏まえ、製品価格を改定すべきか。
- 設備投資の判断:生産性向上のために、新たな設備投資を行うべきか。
質の高い情報が迅速に提供されることで、経営の舵取りはより確実なものとなり、市場の変化に乗り遅れるリスクを最小限に抑えることができます。
経営資源の最適な配分
企業が持つ経営資源、すなわち「ヒト(人材)・モノ(設備など)・カネ(資金)・情報(ノウハウなど)」は有限です。これらの限られた資源を、いかに効率的・効果的に活用するかが、企業の競争力を決定づけます。経営管理の第三の目的は、企業の成長を最大化するために、これらの経営資源を最適な場所に配分(アロケーション)することです。
これは「選択と集中」という戦略的な考え方に基づいています。すべての事業や活動に均等に資源を割り振るのではなく、将来性のある成長事業や、自社の強みが最も活かせる領域に資源を重点的に投入します。一方で、収益性が低い事業や将来性の見込めない事業からは、資源を戦略的に引き揚げる判断も必要です。
経営管理は、予算編成や人員計画、投資計画の策定プロセスを通じて、この資源配分を具体化します。各部門のパフォーマンスを客観的に評価し、全社的な視点から最も効果的な資源の使い道を決定するのです。
| 経営資源 | 最適な配分の具体例 |
| ヒト(人材) | 成長事業へのエース級人材の戦略的配置、DX推進部門へのデジタル人材の重点的な採用・育成 |
| モノ(設備・資産) | 生産性の高い最新鋭の製造設備への投資、活用されていない不動産(遊休資産)の売却 |
| カネ(資金) | 事業ポートフォリオ分析に基づき、将来のキャッシュフロー創出が見込める研究開発(R&D)への重点投資 |
| 情報(データ・ノウハウ) | 蓄積された顧客データを分析し、マーケティング施策を高度化。成功事例や技術ノウハウを全社で共有するシステムの構築 |
このように、経営管理は企業の限りある資源を無駄なく活用し、企業価値の継続的な向上を実現するための根幹をなす活動なのです。
経営管理の具体的な仕事内容をPDCAサイクルで解説
経営管理の業務は、一度行えば終わりというものではありません。企業の持続的な成長を実現するためには、継続的に業務を改善していく必要があります。そのための強力なフレームワークが「PDCAサイクル」です。ここでは、経営管理の具体的な仕事内容を、PDCAサイクル(Plan・Do・Check・Action)の4つのフェーズに沿って詳しく解説します。
計画(Plan):経営計画の策定と予算編成
PDCAサイクルの最初のステップは「計画(Plan)」です。これは、企業の進むべき方向性を定め、具体的な数値目標に落とし込む、経営管理において最も重要なフェーズです。
まず、企業のビジョンや中長期的な経営戦略に基づき、「経営計画」を策定します。市場環境や競合の動向、自社の強み・弱み(SWOT分析など)を多角的に分析し、事業部や部門ごとの具体的な目標を設定します。
次に、策定した経営計画を金銭的な数値で表現する「予算編成」を行います。売上予算、原価予算、経費予算、利益予算などを詳細に作成し、目標達成のための資源配分の計画を立てます。予算は単なる目標数値ではなく、各部門が活動するための指針であり、後の「評価(Check)」フェーズにおける比較基準となる重要なものです。この段階で、現場の意見を吸い上げるボトムアップ方式と、経営層の方針を落とし込むトップダウン方式を組み合わせ、全社的に納得感のある予算を策定することが求められます。
実行(Do):計画に基づいた業務のモニタリング
次のステップは「実行(Do)」です。ここでは、策定された経営計画と予算に基づき、各部門が日々の業務を遂行します。経営管理部門の役割は、自らが業務を直接実行するのではなく、計画通りに事業活動が進んでいるかを継続的に監視(モニタリング)し、必要に応じてサポートすることです。
具体的には、月次や四半期ごとに各部門から業績データの報告を受け、進捗状況を確認します。定期的なレポーティングや会議を通じて、現場で起きている問題や計画との乖離を早期に発見し、経営層へ正確にフィードバックするパイプ役としての機能が重要となります。このモニタリングによって、後の「評価(Check)」フェーズで精度の高い分析が可能になります。
評価(Check):業績評価と予実管理
「評価(Check)」は、実行フェーズの結果を計画フェーズで立てた目標と比較し、その達成度を客観的に評価するステップです。この中心的な業務が「予実管理(予算実績管理)」です。
予実管理では、計画(予算)と実際の業績(実績)を比較し、その差異(ズレ)がどこで、なぜ発生したのかを分析します。この評価を通じて、事業活動が順調に進んでいるのか、あるいは何らかの問題を抱えているのかを定量的に把握します。
KPIによる進捗の可視化
効果的な評価を行うためには、最終目標であるKGI(重要目標達成指標/例:売上高、営業利益率)だけでなく、そこに至るプロセスを測るための中間指標である「KPI(重要業績評価指標)」の設定が不可欠です。
例えば、売上高というKGIを達成するためのKPIとして、「新規商談数」「受注率」「顧客単価」「解約率」などを設定します。KPIを定点観測することで、目標達成に向けた活動の進捗状況が具体的に可視化され、問題の早期発見につながります。これらのKPIは、BIツールなどを活用してダッシュボードでリアルタイムに確認できる状態が理想です。
予実差異分析の手法
予算と実績に差異が生じた場合、「なぜ差異が生まれたのか」を深掘りする「予実差異分析」が重要です。この分析によって、次の「改善(Action)」の精度が大きく変わります。主な分析手法には以下のようなものがあります。
| 分析対象 | 主な分析手法 | 分析内容の例 |
| 売上高の差異 | 価格差異分析・数量差異分析 | 計画より単価を高く販売できたのか(価格差異)、計画より多く販売できたのか(数量差異)などを分析する。 |
| 変動費の差異 | 価格差異分析・能率差異分析 | 原材料の仕入価格が想定より高かったのか(価格差異)、生産効率が悪く材料を多く使ってしまったのか(能率差異)などを分析する。 |
| 固定費の差異 | 予算差異分析 | 人件費や賃料など、当初の予算額と実際の発生額との差額を分析する。 |
これらの分析を通じて、差異の根本原因を特定することが、効果的な改善策を立案するための第一歩となります。
改善(Action):課題の特定と改善策の立案
PDCAサイクルの最後のステップが「改善(Action)」です。評価フェーズで明らかになった課題や差異の原因に基づき、具体的な解決策・改善策を立案し、実行します。
例えば、売上目標が未達で、その原因が「新規商談数の不足」にあると特定された場合、「Web広告の出稿量を増やす」「セミナーを開催してリードを獲得する」といった具体的な改善策を考えます。コストが予算を超過している場合は、「仕入先の見直し」「業務プロセスの自動化による工数削減」などの対策を立案します。
一方で、計画を上回る良い結果が出た場合も、その成功要因を分析することが重要です。「なぜ上手くいったのか」を解明し、そのノウハウを他の部門に展開(横展開)することで、組織全体のパフォーマンス向上に繋げることができます。
ここで立案された改善策は、次の期の「計画(Plan)」に反映されます。このようにPDCAサイクルを継続的に回し続けることで、経営の精度を高め、企業は環境変化に対応しながら持続的に成長していくことができるのです。
経営管理の主な領域と代表的な手法
経営管理は、企業の目指す姿を実現するために、組織内の様々な要素を管理する活動です。その対象は多岐にわたりますが、主に「経営資源」と呼ばれる要素と、それらを効果的に運用するための「管理手法」に大別されます。ここでは、経営管理がカバーする主要な領域と、目標達成のために活用される代表的な手法について詳しく解説します。これらの理解は、自社の経営状況を客観的に把握し、適切な打ち手を講じる上で不可欠です。
管理対象となる4つの経営資源
企業活動の根幹をなすのが「経営資源」です。一般的に、経営資源は「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つに分類され、経営管理はこれらの資源をいかに最適に配分し、最大限の成果を引き出すかを追求します。それぞれの資源には特有の性質があり、管理方法も異なります。
| 経営資源 | 概要と管理のポイント |
| ヒト | 従業員や経営者など、組織を構成する人材を指します。採用、育成、配置、評価、労務管理などを通じて、従業員のモチベーションと生産性を高め、組織全体のパフォーマンスを向上させることが目的です。個々の能力やキャリアプランを考慮した人材マネジメントが、企業の持続的な成長の鍵を握ります。 |
| モノ | 製品やサービスそのものだけでなく、設備、不動産、原材料、備品といった有形の資産全般を指します。生産管理、品質管理、在庫管理、設備管理などを通じて、無駄をなくし、効率的な生産体制を構築することが重要です。適切な在庫管理は、キャッシュフローの改善にも直結します。 |
| カネ | 事業活動に必要な資金(現金、預金、借入金など)を指します。財務管理や資金調達、予算管理、投資判断などが含まれます。企業の血液ともいえる資金を適切に管理し、安定した財務基盤を維持しながら、成長に向けた戦略的投資を実行することが求められます。 |
| 情報 | 顧客データ、販売データ、技術ノウハウ、知的財産、市場動向など、事業活動に関わる無形の資産を指します。現代の経営においてその重要性は増すばかりです。情報セキュリティの確保はもちろん、収集したデータを分析・活用して、新たな価値創造や的確な意思決定につなげる情報マネジメントが不可欠です。 |
代表的な経営管理の手法
4つの経営資源を統合的に管理し、企業のビジョンや戦略を具体的な行動に落とし込むためには、体系化されたフレームワーク(手法)の活用が有効です。ここでは、世界中の多くの企業で導入されている代表的な経営管理の手法を2つ紹介します。
バランススコアカード(BSC)
バランススコアカード(Balanced Scorecard: BSC)は、企業の業績を多角的な視点から評価・管理するためのフレームワークです。従来の財務指標偏重の経営から脱却し、「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」という4つの視点から、業績をバランスよく評価することを目的としています。
これらの視点は相互に関連しており、例えば「学習と成長」(従業員のスキル向上)が「業務プロセス」(生産性の向上)を改善し、それが「顧客」(顧客満足度の向上)に繋がり、最終的に「財務」(売上・利益の増加)の成果として現れる、という因果関係を「戦略マップ」として可視化します。これにより、日々の業務が企業全体の戦略目標にどう貢献しているかを全社で共有しやすくなります。
| BSCの4つの視点 | 概要と指標(KPI)の例 |
| 財務の視点 | 株主や従業員などのステークホルダーに対して、企業が経済的にどのような成果を上げているかを示します。(例:売上高、利益率、キャッシュフロー、ROA) |
| 顧客の視点 | 企業のビジョンを達成するために、顧客に対してどのように貢献すべきかを示します。(例:顧客満足度、新規顧客獲得数、リピート率、ブランド認知度) |
| 業務プロセスの視点 | 顧客満足度や財務目標を達成するために、どのような業務プロセスを構築・改善すべきかを示します。(例:リードタイム、生産性、不良品率、新製品開発サイクル) |
| 学習と成長の視点 | 企業のビジョンを達成するために、組織や個人がどのように変化・成長し続ける必要があるかを示します。(例:従業員満足度、従業員定着率、資格取得者数、改善提案件数) |
重要業績評価指標(KPI)管理
重要業績評価指標(Key Performance Indicator: KPI)管理は、企業の最終目標であるKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)を達成するための、プロセスごとの具体的な行動指標(KPI)を設定し、その進捗を継続的に測定・評価していく管理手法です。
例えば、「年間売上30%増」というKGIを設定した場合、それを達成するための要素を分解し、「月間新規顧客獲得数」「顧客単価」「成約率」といったKPIを設定します。KPIを定期的にモニタリングすることで、目標達成に向けた進捗が順調か、どのプロセスに問題があるかを早期に発見し、迅速な対策を講じることが可能になります。この手法は、前述のPDCAサイクルを効果的に回すための具体的なツールとして機能し、組織全体の目標達成意識と実行力を高める上で非常に有効です。
経営管理の担当者に求められるスキルと知識
企業の羅針盤として、また時には司令塔として経営のかじ取りをサポートする経営管理の担当者には、多岐にわたる高度なスキルと専門知識が求められます。単に数字を扱うだけでなく、それを分析し、組織を動かすための人間力も不可欠です。ここでは、経営管理のプロフェッショナルに必須とされるスキルを「専門知識」「分析能力」「コミュニケーション能力」の3つの側面に分けて詳しく解説します。これらのスキルは相互に関連し合っており、バランス良く身につけることが重要です。
会計や財務に関する専門知識
経営管理の根幹をなすのが、企業の経営状態を数値で正確に把握するための会計・財務知識です。これらは、企業の財政状態と経営成績を客観的に読み解き、将来の経営戦略を立てるための土台となります。勘や経験だけに頼らない、データに基づいた的確な判断を下すために、以下の知識は最低限習得しておく必要があります。
- 財務会計の知識:企業の外部利害関係者への報告を目的とする財務会計の知識は必須です。特に、貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(C/S)から成る「財務三表」を深く理解し、それらの数値を分析して企業の収益性、安全性、成長性を評価する能力が求められます。
- 管理会計の知識:経営者や社内管理者への情報提供を目的とする管理会計は、経営管理業務の核となります。事業部別採算管理、原価計算、ABC(活動基準原価計算)、CVP分析(損益分岐点分析)といった手法を駆使し、予算策定、業績評価、投資判断など、経営の意思決定に直接役立つ情報を作成・提供するスキルが重要です。
- 税務・法務に関する知識:法人税、消費税などの税法に関する基本的な知識や、会社法などの企業活動に関連する法律の知識も必要です。これらを理解することで、税務リスクや法務リスクを考慮した上で、最適な経営判断を下すことができます。
- ファイナンスの知識:資金調達(デットファイナンス、エクイティファイナンス)、企業価値評価(DCF法など)、M&Aといったファイナンス領域の知識も、企業の成長戦略を立案・実行する上で強力な武器となります。
これらの知識を体系的に証明するものとして、日商簿記検定1級、公認会計士、税理士、中小企業診断士といった資格が挙げられますが、資格取得そのものが目的ではなく、あくまで実務で活かせる深い理解が大切です。
データ分析能力と論理的思考力
現代の経営管理において、会計情報や販売データ、市場データといった膨大な情報を適切に処理・分析し、経営判断に資するインサイトを導き出す能力は不可欠です。客観的な事実(ファクト)に基づき、課題の本質を見抜いて最適な経営判断を導き出すための必須スキルと言えるでしょう。
- データハンドリング能力:ERPや会計システム、販売管理システムなど、社内外の様々なソースから必要なデータを抽出し、分析しやすいように加工・整形するスキルです。Excelの高度な関数(VLOOKUP、SUMIFS、ピボットテーブルなど)やマクロ(VBA)の知識、さらにはデータベースを操作するためのSQLの知識があると、より効率的に業務を進められます。
- 統計的な分析能力:収集したデータを前に、その背景にある傾向や相関関係、因果関係を統計的な手法を用いて見つけ出す能力です。平均や分散といった基本的な統計量だけでなく、回帰分析などの手法を理解していると、より精度の高い需要予測や要因分析が可能になります。
- 論理的思考力(ロジカルシンキング):分析結果から何が言えるのか、課題の真因はどこにあるのかを筋道立てて考える力です。MECE(ミーシー:漏れなくダブりなく)やロジックツリーといったフレームワークを活用し、複雑な事象を構造的に整理して、説得力のある結論を導き出すことが求められます。
- データの可視化能力:分析によって得られたインサイトを、経営層や関連部署のメンバーに分かりやすく伝えるためのスキルです。グラフやチャートを効果的に用いて、複雑なデータも直感的に理解できる形にまとめる表現力が重要となります。
高いコミュニケーション能力
経営管理の仕事は、分析や計画策定だけで完結しません。その内容を関係各所に伝え、理解と協力を得て、全社的なアクションへと繋げていく必要があります。そのため、専門知識や分析結果を具体的なアクションに繋げ、組織全体を動かすための潤滑油となるのがコミュニケーション能力です。立場や専門分野の異なる多様な人々と円滑に連携し、目標達成に向けて組織を一つにまとめる力が求められます。
具体的には、以下のような多面的なコミュニケーション能力が重要となります。
| 求められる能力 | 具体的な内容と重要性 |
| プレゼンテーション能力 | 経営会議などの場で、分析結果や計画案を経営層に分かりやすく説明し、納得してもらうための能力です。単に情報を羅列するのではなく、論理的なストーリーを組み立て、聞き手の意思決定を促すことがゴールとなります。 |
| 交渉・調整能力 | 予算配分や目標設定の際に生じる各部署間の利害対立を調整し、会社全体の利益が最大化される着地点を見出す能力です。相手の立場を理解しつつ、自部門の主張を論理的に展開し、合意形成を図る粘り強さが求められます。 |
| ヒアリング能力 | 現場の従業員や各部門の責任者から、課題やボトルネック、改善のアイデアなどを引き出す能力です。現場の実態を正確に把握することが、実効性の高い計画を策定する上での大前提となります。傾聴力とも言い換えられます。 |
| ファシリテーション能力 | 会議やワークショップを円滑に進行し、参加者から活発な意見を引き出して議論を活性化させ、時間内に建設的な結論へと導く能力です。中立的な立場で議論を整理し、全員が納得できる合意形成をサポートする役割を担います。 |
経営管理を効率化するツール
現代の経営管理は、膨大かつ複雑なデータを迅速に処理し、正確な意思決定に繋げることが求められます。Excelや手作業による管理には、属人化のリスク、集計作業の非効率さ、リアルタイム性の欠如といった限界があります。そこで、これらの課題を解決し、経営管理の質とスピードを飛躍的に向上させるのがITツールです。ここでは、経営管理を効率化・高度化するために不可欠な代表的なツールを紹介します。
ERP(統合基幹業務システム)の活用
ERP(Enterprise Resource Planning)とは、「企業資源計画」と訳され、企業経営の根幹となる「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を統合的に管理し、その最適化を図るためのシステムです。会計、人事、生産、販売、在庫管理など、各部門で個別に管理されていた情報を一元化する点が最大の特徴です。
経営管理においてERPを活用することで、以下のような大きなメリットが得られます。
- 経営データのリアルタイムな一元管理
全部門のデータがリアルタイムにERPへ集約されるため、経営層はいつでも正確な経営状況を把握できます。部門間のデータのサイロ化(分断)を防ぎ、全社横断的な視点での迅速な意思決定を強力に支援します。 - 業務プロセスの標準化と効率化
全社で統一された業務プロセスとデータ形式が適用されるため、業務の標準化が促進されます。これにより、内部統制の強化に繋がるだけでなく、二重入力や無駄な確認作業といった非効率な業務が削減されます。 - 経営分析の精度向上
信頼性の高い統合データが蓄積されるため、精度の高い経営分析や将来予測が可能になります。正確なデータに基づいた予算編成や事業計画の策定に大きく貢献します。
BI(ビジネスインテリジェンス)ツールの活用
BI(Business Intelligence)ツールは、企業内に散在する様々なデータを集約・分析・可視化し、経営や事業の意思決定に役立てるためのツールです。ERPがデータを「集約・統合する」システムであるのに対し、BIツールは蓄積されたデータを「分析・可視化する」ことに特化しています。
経営管理におけるBIツールの主なメリットは以下の通りです。
- データの直感的な可視化(経営ダッシュボード)
売上推移、利益率、KPIの達成状況といった重要な経営指標を、グラフやチャートを用いて視覚的にわかりやすく表示する「経営ダッシュボード」を作成できます。専門的な知識がなくても、経営状況を一目で直感的に把握することが可能です。 - 多角的で自由なデータ分析
気になる数値をクリックするだけで詳細な内訳を表示する「ドリルダウン」や、分析の切り口を自由に変える「スライシング」といった機能により、問題の原因究明や新たなビジネスチャンスの発見に繋がる多角的な分析を容易に行えます。 - レポーティング業務の自動化
これまで手作業で作成していた月次報告書や業績レポートなどを自動で生成できます。これにより、経営管理部門の担当者はデータ集計作業から解放され、より付加価値の高い分析業務に集中できます。代表的なツールには、Microsoft Power BI、Tableau、Looker Studioなどがあります。
その他の経営管理に役立つ専門ツール
ERPやBIツール以外にも、特定の経営管理業務に特化した専門ツールを組み合わせることで、さらなる効率化と高度化が期待できます。
| ツールの種類 | 主な機能と導入メリット |
| 予算管理システム | 予算編成、予実管理、見込管理に特化したシステム。Excel管理で起こりがちな集計ミスやバージョン管理の煩雑さを解消し、精度の高い予算策定とタイムリーな予実分析を実現します。複数のシナリオを想定したシミュレーション機能も強みです。 |
| SFA/CRM | SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)は、営業活動や顧客情報を管理するツールです。蓄積された商談データや顧客データは、売上予測の精度向上や顧客別の収益性分析など、経営管理の重要な情報源となります。 |
| プロジェクト管理ツール | プロジェクトごとの進捗、工数、コストを管理するツール。特にプロジェクト単位で事業を行う企業において、プロジェクト別の採算性を正確に把握し、経営資源の最適な配分を判断するために不可欠です。 |
経営管理ツールの選び方と導入のポイント
自社に最適な経営管理ツールを導入し、その効果を最大化するためには、いくつかの重要なポイントがあります。単に多機能なツールを選べば良いというわけではありません。
ツール選定時には、以下の点を総合的に評価し、自社の目的と状況に最も合致するものを選ぶことが成功の鍵となります。
| 選定ポイント | 具体的な確認事項 |
| 目的の明確化 | 「なぜツールを導入するのか」を明確にします。「予実管理を効率化したい」「経営状況をリアルタイムで可視化したい」「データ分析の属人化を解消したい」など、解決したい課題を具体的にリストアップします。 |
| 機能の過不足 | 明確化した目的に対して、必要な機能が備わっているかを確認します。逆に、不要な機能が多すぎるとコストが高くなったり、操作が複雑になったりするため、自社の規模や業態に合ったツールを選びます。 |
| 操作性と定着のしやすさ | 経営層や管理者だけでなく、実際にデータを入力・活用する現場の従業員が直感的に使えるかどうかが、ツール定着の最も重要な要素です。無料トライアルなどを活用し、実際の使用感を確認することが推奨されます。 |
| 連携性と拡張性 | 現在使用している会計ソフトや基幹システムなど、他のシステムとスムーズにデータ連携できるかを確認します。また、将来の事業拡大や組織変更にも柔軟に対応できる拡張性があるかも重要な選定基準です。 |
| サポート体制とコスト | 導入時の設定支援や導入後の操作トレーニング、トラブル発生時のサポート体制が充実しているかを確認します。初期費用だけでなく、月額利用料や保守費用を含めたトータルコストで比較検討することが大切です。 |
まとめ
経営管理とは、企業のビジョンや目標を達成するために、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を最適に配分し、組織全体の活動を調整する、企業の成長に不可欠な羅針盤です。その役割はPDCAサイクルを通じて計画から改善まで多岐にわたります。変化の激しい現代市場で企業が持続的に成長し、競争優位性を確立するためには、データに基づいた的確な経営管理体制の構築が極めて重要と言えるでしょう。
- カテゴリ:
- 経営/業績管理
- キーワード:
- 予実管理